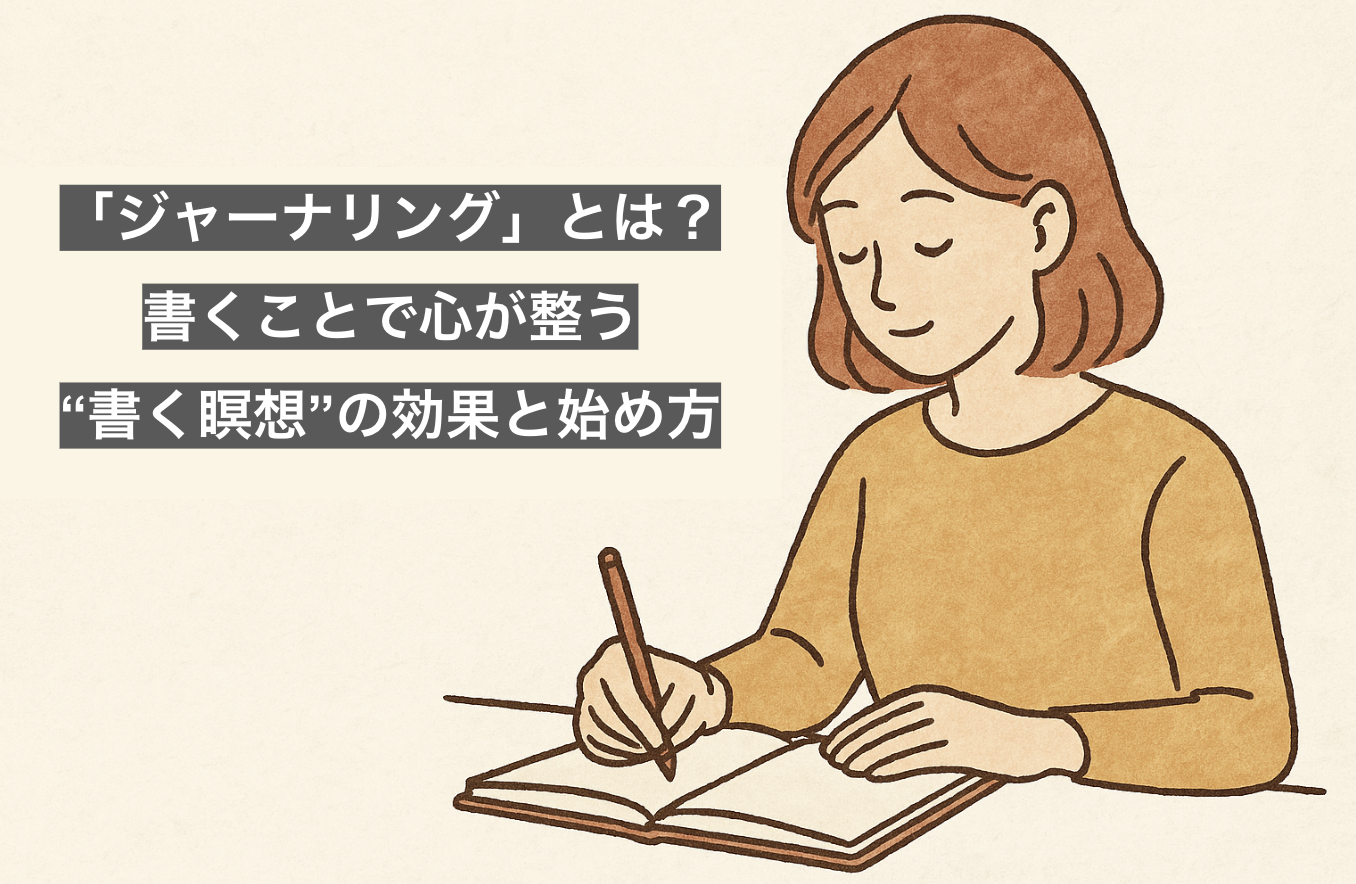「なんだか最近、心がざわざわする」
「気持ちを整理したいのに、うまく言葉にならない」
そんなときに、ただ“書く”というシンプルな行為が、驚くほど心を整えてくれることがあります。
この記事では、「ジャーナリング」や「書く瞑想」と呼ばれる、自分自身の心と向き合うセルフケアの方法について、心理カウンセラーの視点からやさしくご紹介していきます。
ジャーナリング・書く瞑想とは?
はじめに|“書く”という小さな習慣が、心に変化をもたらす
「気持ちを整理したいのに、うまく言葉にならない」
そんなときにおすすめしたいのが、「ジャーナリング」や「書く瞑想」といった、書くことで心と向き合うセルフケアです
特別な準備は必要ありません。紙とペン、あるいはスマートフォンのメモアプリだけで、自分の心にそっと耳を傾ける時間をつくることができます。
ここでは、ジャーナリングの意味や「書く瞑想」との違い、そしてマインドフルネスとのつながりをやさしく解説していきます。
ジャーナリング=「書く」ことで心を整えるセルフケア
ジャーナリングとは、自分の感じたことや考えたことを、自由に書き出す行為のことです。
日記とは少し違い、「何を書かなければいけない」という決まりはありません。
テーマも自由。
今日あったこと、モヤモヤしている気持ち、ふと思い出した記憶、自分への問いかけ——すべてが書く対象になります。
なぜ“書くこと”が心に効くのか?
心理学では、「感情のラベリング」という概念があります。
これは、自分の感情を言葉にすることで、脳の扁桃体の過剰な反応が落ち着き、感情が整理されるというものです(医学論文)
つまり、言葉にすることで心が少し落ち着き、“客観視”する力が育つのです。
また、頭の中でぐるぐるしている思考を書き出すことで、「見える化」され、漠然とした不安が明確になることもあります。
これにより、問題解決の糸口が見えてきたり、自分の思考のクセに気づけることがあります。
■こんなときにおすすめです
- イライラや不安など、感情が高ぶっているとき
- 人間関係でモヤモヤを感じているとき
- 考えがまとまらないとき
- 前向きになりたいけど気力が湧かないとき
誰かに話すのは難しくても、紙になら素直に打ち明けられる——そんな感覚で続けられるのが、ジャーナリングの良さでもあります。
■効果的なジャーナリングのテーマ例
「何を書けばいいかわからない」という声もよく聞きます。
でも、もし迷ったときは、以下のようなテーマから始めてみてください。
| テーマ | 書き方のヒント |
|---|---|
| 今日の出来事と感じたこと | 時系列でも、感情中心でもOK |
| 嬉しかったこと・感謝していること | ポジティブな記憶を意識的にすくい上げる |
| 今の自分への問いかけ | 「本当はどうしたい?」など自分に質問する形 |
日によって書く内容が変わっても構いません。
「うまく書こう」とするよりも、「正直に書こう」と思うことのほうが、心にはやさしく響きます。
- ジャーナリングは、感じたこと・考えたことを自由に書くことで、心を整える手法です
- 書くことで感情をラベリングし、脳のストレス反応を和らげる効果が期待されます
- 書くことに正解はなく、自分自身と向き合う時間を大切にすることが本質です
「書くだけでそんなに変わるの?」と、まだ半信半疑かもしれません。
次の章では、実際にジャーナリングや書く瞑想によって得られる効果について、心理学的な知見や実例を交えて詳しく解説していきます。
どんな効果があるの?(エビデンス付き)
“書くこと”がもたらす、心へのやさしい変化
「ジャーナリングや書く瞑想って、実際どんな効果があるの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
ただ思ったことを書く、気持ちを書き出す——そのシンプルな行為が、なぜ心を整えることにつながるのか。
ここでは、心理学や精神医療の分野で確認されている科学的な根拠(エビデンス)を交えながら、書くことがもたらす代表的な3つの効果について、やさしく解説していきます。
■「書く」ことで感情に名前をつけると、心が静まる
私たちは日々、さまざまな感情を抱いています。
怒り、悲しみ、不安、焦り…。
でも、それらの感情に振り回されるばかりで、「自分が何を感じているのか」がわからなくなることもあるのではないでしょうか。
ジャーナリングの大きな効果のひとつは、感情を“外に出す”ことで、整理しやすくなるという点です。
冒頭でも述べましたが、心理学ではこれを「エモーション・ラベリング(感情へのラベル付け)」と呼びます。
言葉にするだけで脳内の扁桃体(情動を司る部位)の反応が抑えられ、前頭前野が活性化し、冷静さが戻ってくるとされています。
■日々のストレスを「見える化」することで、客観視ができる
ジャーナリングは、そうした漠然とした感情や思考を“言葉という形”にすることで、頭の中の混乱を整理し、心にスペースをつくる方法です。
たとえば、怒りや不安、悲しみなどの「ネガティブ」と呼ばれる感情も、そのまま書いて大丈夫です。
むしろ、抑え込まずに言葉にしてあげることで、少しずつ落ち着きが戻ってきます。
これは心理学で「感情の外在化」と呼ばれ、自分の気持ちとの間に少し距離をとることで、冷静さを取り戻しやすくなるとされています。
成功体験や感謝を記録することで、肯定感が育つ
ネガティブな気持ちを書くだけでなく、日々の中で「よかったこと」「感謝できたこと」「頑張った自分」も言葉にして残しておくことは、自己肯定感を育てるうえでとても大切です。
これは「感謝日記」や「ポジティブジャーナリング」として、ポジティブ心理学の分野でも効果が認められています。
ある研究では、参加者を3つのグループに分け、週に一度「感謝したこと」「困難な出来事」「中立的な出来事」を記録してもらいました。
その結果、「感謝したこと」を記録したグループは、他のグループに比べて主観的幸福感が高まり、身体的健康状態も良好であると報告されました。(引用論文)
たとえばこんな書き方から始めてみましょう:
- 今日嬉しかったことを3つ書く
- 「ありがとう」と思った出来事や人を1つ書く
- 今日の自分に、ねぎらいの言葉をかける(例:「よく頑張ったね」「少し休もうね」)
小さな喜びや達成感に意識を向ける習慣は、「できないこと」ばかりに目を向けがちな思考パターンを、少しずつ柔らかくしてくれます。
■抑うつ感の軽減に有効という研究報告
2005年に発表されたBaikie & Wilhelmのメタ分析では、「表現的ライティング(感情を自由に書くこと)」を取り入れた人たちにおいて、抑うつ症状の有意な改善が確認されました。(引用論文)
論文では、表現的ライティング(感情やストレスに関する出来事を自由に書くこと)が身体的および心理的健康に与える影響についての研究を総括しています。
特に、抑うつ症状の改善や免疫機能の向上、ストレス関連の症状の軽減など、多岐にわたる健康上の利益が報告されています。
- 書くことで感情の整理ができ、脳のストレス反応を落ち着かせる効果がある
- 自分との対話を通じて、自己理解や自己肯定感が育つ
- ジャーナリングや書く瞑想は、不安や軽度の抑うつ感の軽減にもつながるとする研究が複数ある
効果がわかっても、「実際に何を書けばいいの?」「うまく続けられるかな…」と迷う方も多いかと思います。
次の章では、ジャーナリングや書く瞑想の具体的な始め方や書き方の例をご紹介していきます。
はじめてのジャーナリングガイド
はじめに|少しの準備と気持ちがあれば、誰でも始められる
「ジャーナリングって難しそう」
「何を書けばいいのかわからない」
——そんな声をよく耳にします。
でも、実はジャーナリングは、特別なルールや道具がいらない、誰にでもできるメンタルケアです。
この章では、ジャーナリングをこれから始める方のために、必要なもの、実践のタイミング、初心者におすすめの書き方のパターンなどを、やさしく丁寧にご紹介します。
必要なものは?ノートとペンだけでOK
ジャーナリングの素晴らしいところは、特別な準備や知識がなくても、今すぐ始められるということです。
必要なのは、以下のものだけです:
| 必要なもの | 理由 |
|---|---|
| ノートまたは紙(自由帳でもOK) | 思ったこと、感じたことを制限なく自由に書ける場所。文字の多さや正しさは気にしなくて大丈夫です。 |
| ペン・鉛筆などの筆記具 | キーボード入力より、手書きのほうが感情が整理されやすいという研究もあります。 筆圧や字の揺らぎは、自分の気持ちの“声”のようなものです。 |
| 落ち着ける空間と数分の静かな時間 | たとえ5分でも、「自分のために過ごす」穏やかな時間をつくってあげることで、心がふっと和らぐことがあります。 |
もし余裕があれば、お気に入りのノートや万年筆など少し気分が上がるものを選ぶと、書くことが楽しみになりますんで自分の気分を高めるアイテムを取り入れてみるのもおすすめです。
いつ、どのくらい書けばいい?
「ジャーナリングは朝がいい? 夜がいい?」という質問をよくいただきますが、答えは「自分にとって落ち着ける時間がベスト」です。
時間帯に決まりはありません。大切なのは、「この時間なら書いてみようかな」と思える瞬間を見つけることです。
| 時間帯 | 特徴 |
|---|---|
| 朝起きてすぐ | 頭がまだ整理されておらず、無意識の本音が浮かびやすい。 創造性が高まりやすく、1日の気持ちを整えるのにぴったりです。 |
| 夜寝る前 | 1日の出来事を振り返ったり、感謝や安堵の感情に目を向けることで、気持ちよく眠りにつける人もいます。 |
■1日5分からでも十分。
「毎日続けなきゃ」と思うと、かえって書くことがプレッシャーになってしまいます。
たった数分でも、自分の気持ちと向き合えたと思えれば、それで十分です。
大事なのは「どれだけ書いたか」ではなく、「自分の心に触れたかどうか」。
無理のない範囲で、「今日はちょっとだけ書こうかな」という気持ちを、そっと大切にしてみてください。
初心者におすすめの書き方例(3パターン)
はじめのうちは「何を書けばいいの?」と迷うこともあるかもしれません。
ここでは、初心者でも気軽に取り組める3つのジャーナリングのスタイルをご紹介します。
書き方1. モーニングページ(脳のデトックス)
【方法】
朝起きてすぐ、思考が動き出す前の時間に、ノートに3ページ分、思いつくまま手を動かして書いていきます。
内容にルールはありません。
「眠い」「夢を見た」「今日やることが嫌だ」など、どんな言葉でもOKです。
【効果】
- 頭の中にたまっていた思考や感情が自然に整理される
- 心のモヤモヤが外に出ることで、スッキリとした気分で1日を始められる
- 創造性が刺激され、新しいアイデアが浮かびやすくなることも
【ポイント】
・書いたものは読み返す必要はありません。・“うまく書こう”とせず、“思ったまま書く”ことに意味があります。
書き方2. 感情日記(気持ちに寄り添う)
【方法】
その日あった出来事や、自分が感じた感情を中心に書いていくスタイルです。
【書き方の例】
- 「今日は〇〇にイライラした。なぜかというと…」
- 「〇〇と言われて悲しかったけど、それは私が気にしていることだったのかもしれない」
【効果】
- 自分の感情を“気づき、受け止める”練習になる
- 無意識の感情や反応パターンを、少しずつ客観視できるようになる
書き方■3. 感謝ジャーナル(前向きな視点を育てる)
【方法】
その日に「感謝できたこと」「よかったこと」を3つ書くだけの、シンプルな習慣です。
【効果】
- 小さな幸せに気づく力が育ち、ポジティブな視点が自然と増えていく
- ストレスへの耐性が高まる
【書き方の例】
- 「駅までの道で咲いていた花に癒された」
- 「コンビニの店員さんが笑顔でありがとうと言ってくれた」
- 「今日もごはんを食べられたことに感謝」
意識的に“今”に集中する書き方:「マインドフル・ジャーナリング」
“今この瞬間”に意識を向けて書く「マインドフル・ジャーナリング」は、不安や思考の暴走を落ち着ける助けになります。
感情や身体感覚に目を向けながら書くことで、自分の“今”を穏やかに受け止められるようになります。
【書き方のステップ】
- 深呼吸を数回して、体の緊張をゆるめます
- 「今、どんな感情がある?」「体はどんな感覚?」と静かに問いかけます
- 思いついたまま、否定せずに言葉にして書いてみましょう
例:「胸がちょっと重たい」「気が散っているけど、落ち着いてきた気もする」
このように、自分の“今”をそのまま受け止めて書くことで、不安や緊張がやわらぎやすくなります。
五感・感情に注意を向ける書き方のコツ
五感は、心と体を“今ここ”につなぎとめてくれる大切なツールです。
意識を向けるだけで、心が自然と静まりやすくなります。
【フレーズ例】
- 「今、見えているものは……」
- 「聞こえてくる音は……」
- 「身体が感じている感覚は……」
- 「その感覚に重なっている気持ちは……」
言葉にすることで、「私はここにいて、感じている」という感覚が育ちます。
これは、不安や落ち込みで“今”にいられないときにも、とても効果的です。
「リフレクション」:書いたあとの“振り返り”が、心の成長につながる
ジャーナリングの魅力は「書く」だけでは終わりません。
ときには、書いた内容を読み返すことで、自分の思考や感情の変化に気づくこともあります。
【リフレクションの視点例】
- 「書いてみて、何に気づいたか?」
- 「この気持ちは、どこから来ていたのだろう?」
- 「少しだけでも、気持ちは落ち着いただろうか?」
リフレクション(内省)は、自分自身との“対話の続きを深める時間”でもあります。
できれば数日経ってから読み返すと、より客観的に、優しいまなざしで自分を見られるかもしれません。
- ジャーナリングは、ノートとペンがあればすぐに始められる
- 朝や夜の静かな時間に、1日5分程度からでOK
- 初心者には、モーニングページ・感情日記・感謝ジャーナルの3パターンがおすすめ
- 書くときは、“今”の自分の感覚や感情に意識を向けることが大切
次の章では、ジャーナリングを無理なく続けていくためのコツや、よくあるつまずきへの対処法についてご紹介します。
継続が難しく感じるときこそ、自分にやさしく寄り添うヒントを見つけていきましょう。
続けるコツと注意点
ジャーナリングは、心と向き合う大切な時間。
けれども、続けようと思えば思うほど、「今日も書けなかった…」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
この章では、ジャーナリングを無理なく続けていくための考え方や注意点についてお伝えします。
「書かない日」があっても、それもまた自然なこと
「毎日書かなきゃ…」「継続しないと意味がないのでは?」と感じてしまう方は少なくありません。
ですが、ジャーナリングは義務ではなく、自分の心に寄り添うための時間。
無理をして書こうとすると、かえって負担になり、書くこと自体がストレスになってしまうこともあります。
続かないからといって、意味がないわけではありません。
1回のジャーナリングで、大きな気づきや癒しが生まれることもあります。
■週に1回でもOK。自分のペースで習慣化を目指す
心理学的にも、習慣化において大切なのは「完璧さ」ではなく「柔軟さ」です。
たとえば次のように、自分の生活に合わせた“マイルール”を設けると、気持ちが楽になるかもしれません。
- 「週に3回、寝る前に10分だけ書く」
- 「休日の朝にコーヒーを飲みながら書く」
- 「気持ちが揺れたときだけ書く」
ネガティブな感情が出ても否定しない
ジャーナリングを続けていると、怒り、悲しみ、焦り、嫉妬、不安…といったネガティブな感情がたくさん出てくることがあります。
それは、あなたが“感じること”を許し始めた証拠です。
感情は、良い・悪いではなく、「ただのサイン」です。
心の奥で、何かが満たされていなかったり、傷ついていたりすることに気づくヒントなのです。
■“感じきる”ことで、次第に感情は変化していく
「私たちの心は、感情をただ抑え込むのではなく、“ちゃんと感じてあげること”で、少しずつ落ち着いていく力を持っています。感じきられた感情は、そこで完結して、そっと癒されていくのです。」
トラウマ治療の分野でも、抑圧された感情を安全な場でゆっくりと感じ直すことが、神経系の再調整と癒しに結びつくと考えられています。(医学論文)
書くことで一時的に気持ちが重くなることもありますが、それを言葉にすることで、心が少しずつ整理され、癒しが始まっていくのです。
■感情を否定しないためのフレーズ例
書いている途中で苦しくなったときは、次のような言葉を添えてみてください。
- 「今はこんなふうに感じている自分がいるんだな」
- 「この気持ちにも、理由があるのかもしれない」
- 「否定せずに、ただ受け止めてみよう」
■どうしてもつらいときは、誰かに話してもいい
書くことがつらくなったときは、一人で抱えこまず、信頼できる人や専門家に気持ちを話してみてください。
ジャーナリングは“ひとりで頑張る”ためのツールではなく、“自分を支える”ひとつの手段です。
誰かに相談したい時はこちらの記事を読んでみてください → 【専門家が解説】うつ・ストレスで悩んだら相談を|カウンセリングの受診目安・種類・流れの完全ガイド
- ジャーナリングは「毎日書かなければならない」ものではありません
- 自分の生活リズムに合わせて、無理のない頻度で続けることが大切
- ネガティブな感情は、抑えるのではなく「感じて、書く」ことで癒されていきます
- 書いたことを否定せず、「これが今の自分なんだ」と受け止めてあげましょう
最後に
私たちの心は、ときに「書くこと」によって、自分自身をそっと受け止める力を取り戻します。
たとえ数行でも、今感じていることを言葉にするだけで、少し肩の力が抜ける瞬間が訪れるかもしれません。
ジャーナリングや書く瞑想は、誰にでもできる、優しい心のメンテナンスです。
日々の中に、自分だけの“静かな対話の時間”をつくってみませんか?その積み重ねが、あなたの心を少しずつ整え、今日という一日を、ほんの少し穏やかにしてくれるはずです。
【合わせて読みたい関連記事】
・「心の疲れ」と「心労」を感じたときに知っておきたいこと|専門家が教えるセルフケアと向き合い方