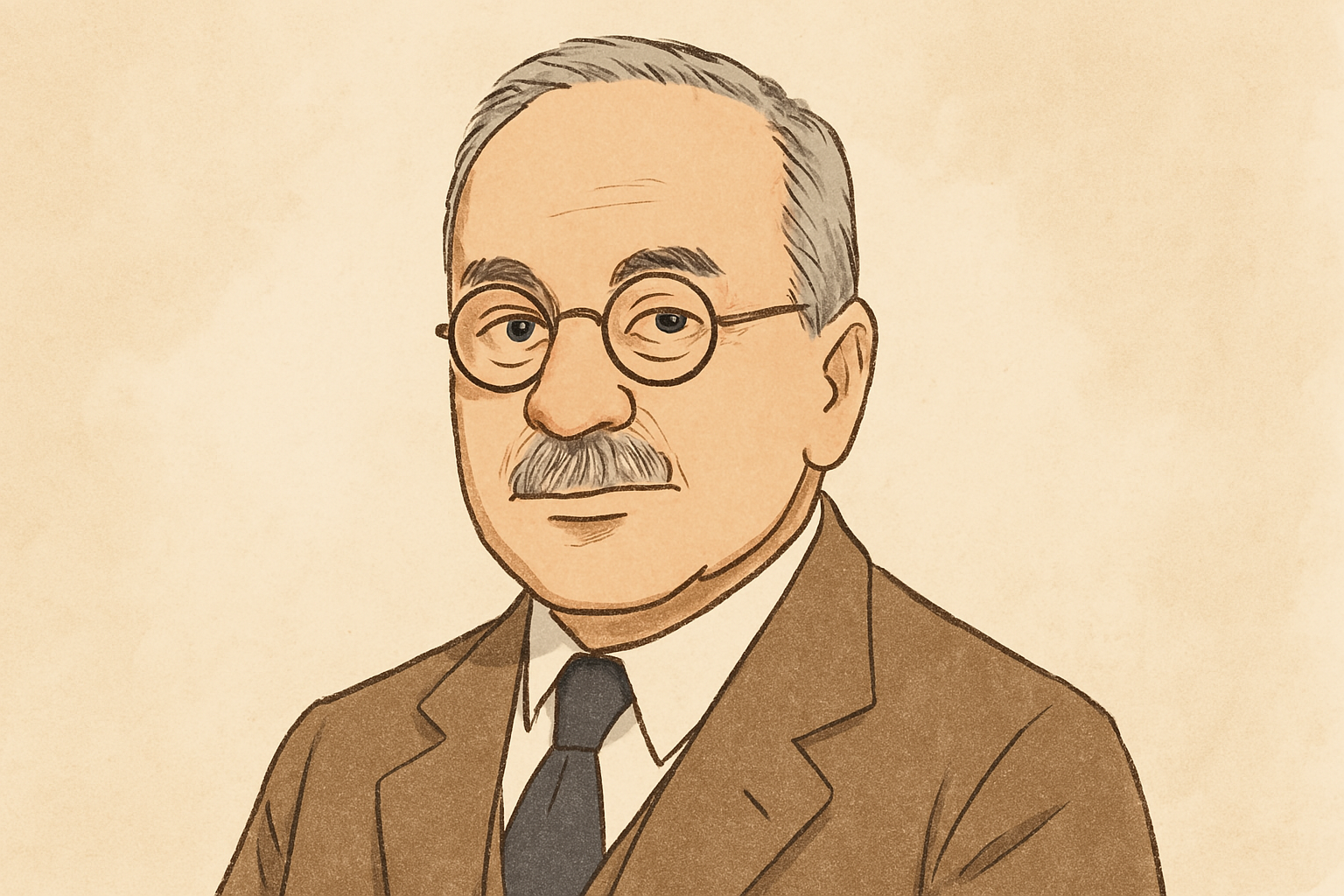「嫌われる勇気」というベストセラーをきっかけに注目を集めたアドラー心理学。
けれど、その土台にある思想や創始者であるアルフレッド・アドラーについて、詳しく知る機会は多くありません。
アドラーは「すべての悩みは人間関係にある」と説いた、20世紀初頭の精神科医です。
彼の人生観や心理学は、単なる治療理論ではなく、“生き方の哲学”として、現代にも多くのヒントを与えてくれます。
この記事では、アドラー自身の生涯や思想から、彼の築いた心理学の核心、そして実生活への応用までを、やさしく丁寧にひもといていきます📚🌱
第一章:アルフレッド・アドラーという人物 ― その思想と生涯
アドラー心理学を理解するうえで欠かせないのが、創始者アルフレッド・アドラーという人物の人生そのものです。
彼の経験や時代背景を知ることで、なぜ「劣等感」や「共同体感覚」といった概念が生まれたのか、より深く理解できます。
この章では、アドラーの生い立ちからフロイトとの決別、彼の哲学的な人生観、そして教育・医療現場での実践的な活動までをご紹介します。
理論だけでは見えてこない、人間・アドラーの魅力を感じてみてください。
生い立ちと時代背景
アルフレッド・アドラーは1870年、オーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーンに生まれました。
当時のウィーンは、芸術や学問が花開く一方、経済的な格差や社会的な緊張も高まっていた時代。そんな中でアドラーは、ユダヤ系の中流家庭に育ちます。
幼少期にはくり返し重い病気にかかり、5歳のときには肺炎で生死をさまよう体験をしました。
これが、のちに彼が唱える「劣等感」の概念の原体験になったとされています。
青年期には医師を志し、眼科・内科を経て精神医学の分野へと進みます。
彼が見つめ続けたのは、“なぜ人は苦しみ、それでも前に進もうとするのか”という問いでした。
フロイトとの訣別:なぜ精神分析学を離れたのか
アドラーは初期にはジークムント・フロイトの精神分析グループの一員として活動していました。
しかし、彼の思想は次第にフロイトとは異なる方向を示し始めます。
| 対比 | フロイト | アドラー |
|---|---|---|
| 人間理解の中心 | 無意識・性的衝動 | 社会性・目的意識 |
| 問題の原因 | 過去のトラウマ | 現在の目的と行動 |
| 方法論 | 精神分析 | 個人心理学(Individual Psychology) |
アドラーは、人間を“過去に支配される存在”ではなく、“目的に向かって生きる存在”として捉えました。
この立場の違いから、1911年にフロイトのグループを離れ、自身の理論「個人心理学(Individual Psychology)」を確立します。
アドラーの理論の中核にあるのが「劣等感」です。
彼自身が兄に比べて身体が弱く、何かと比較されて育った経験が、“劣等感が人を動かす力になる”という考えにつながったといわれています。
📌 アドラーが説く「劣等感」の特徴
- 劣等感そのものは悪いものではない
- 劣等感があるからこそ、人は成長・補償しようと努力する
- ただし、過剰になると「劣等コンプレックス」となり、苦しみを生むことも
アドラー心理学では、「人は“自分の意味づけ”によって現実をとらえている」と考えます。
そのため、劣等感をどう受け止めるかが、その人の生き方に大きな影響を与えるのです。
「社会とのつながり」を重視した生涯哲学
アドラーは、人間を「社会的な存在」としてとらえました。
彼が大切にした概念が「共同体感覚」です。
これは、「他者とのつながりを感じながら、自分の人生を主体的に歩む」という考え方であり、
アドラーはそれを「人間としての成熟」の指標としました。
- 他者を敵ではなく仲間と見なす
- 社会に貢献しようとする姿勢
- 「所属感」や「信頼感」を持って生きる
この思想は、現代のポジティブ心理学や教育論にも大きな影響を与えています🕊️
アドラーは「学問としての心理学」にとどまらず、教育・カウンセリング・医療・軍隊など、あらゆる現場で実践的な活動を行いました。
- 子どもの行動問題に対する「勇気づけ」的アプローチ
- 教師・親への心理教育(ペアレンティングの先駆け)
- 戦後の社会復興支援としての心理相談活動
- 民主主義的なリーダーシップ教育への影響
特に子どもへのまなざしは一貫しており、「叱らない・命令しない・共感する」関わり方を早くから提唱していました。
- アルフレッド・アドラーは、病弱な幼少期と比較に苦しんだ経験から「劣等感の心理学」を築いた
- フロイトとは異なり、目的志向で社会性を重視する“人間の可能性”を信じた立場を取った
- 人間は「変われる」存在であり、他者とつながることでその力を発揮できると考えた
- 教育・医療・戦後復興など、現場での実践を重視した心理学者だった
アルフレッド・アドラーの思想には、「人は変われる」という力強い信念がありました。
では、彼が生涯をかけて築いた「アドラー心理学」とは、一体どのような理論なのでしょうか?
次章では、「劣等感」「共同体感覚」「課題の分離」「勇気づけ」など、アドラー心理学を構成する重要なキーワードを丁寧にひもときながら、その基本理論と特徴をやさしく解説していきます🧩📖
第二章:アドラー心理学とは何か? ― その基本理論と特徴
アルフレッド・アドラーが築いた心理学は、単なる精神疾患の治療理論ではなく、私たちの生き方そのものに深く関わる哲学的な心理学です。
「どうすれば人は前向きに生きられるのか」「人間関係の悩みをどう乗り越えるか」といった問いに対して、アドラーは実践的な答えを示しました。
この章では、アドラー心理学を理解する上で欠かせない5つのキーワード―「劣等感」「ライフスタイル」「目的論」「課題の分離と共同体感覚」「勇気づけ」を、やさしく解説していきます🧩
劣等感と補償:誰もが「何かが足りない」から成長できる
アドラー心理学の出発点は、「人は誰しも劣等感を持っている」という考え方です。
この“劣等感”は、欠点や弱さとして否定的にとらえられがちですが、アドラーにとっては成長や努力の原動力でした。
たとえば、「自分は人前で話すのが苦手だ」と感じる人が、そのコンプレックスを補うために努力して、プレゼン力を磨いたり、文章で表現したりします。
このように、劣等感は「補償」という形で、私たちをより良い方向へと動かすエネルギーになるのです。
ただし、劣等感が過剰になると「劣等コンプレックス(自分はダメだという思い込み)」や「優越コンプレックス(過度に偉そうに振る舞う)」として、対人関係に問題を起こすこともあります。
🧠劣等感とのつきあい方は、アドラー心理学の大切な基盤です。
ライフスタイル理論:人生の意味づけのクセを見る
アドラー心理学では、「ライフスタイル」という概念が重要です。
これは洋服のセンスのような“生活様式”ではなく、その人がどのように世界を見て、自分の位置づけをしているかという“人生観”を意味します。
たとえば…
- 「私は誰にも頼れない」というライフスタイルを持っている人は、助けを求めるのが苦手かもしれません
- 「人に好かれていなければ価値がない」と思い込んでいる人は、無理して頑張りすぎてしまうかもしれません
このように、私たちは無意識に“自分なりの意味づけ”をもとに行動しているのです。
アドラー心理学では、自分のライフスタイルに気づき、それを見直すことで、行動や思考を変えることができると考えます。
目的論:過去よりも「これからどうするか」を重視する考え方
フロイトが「過去のトラウマが人を支配する」と説いたのに対し、アドラーは「人は未来の目的に向かって行動する」と考えました。これを目的論といいます。
たとえば…
- 怒りっぽい人は、「自分を守るために怒りという手段を使っている」
- 落ち込みがちな人は、「自分を責めることで責任を回避している」
というように、行動には“今の自分にとって都合のいい目的”があると見るのです。
この考え方は、「なぜそうなったのか(原因)」ではなく、「どうしたいのか(目的)」に視点を向けるため、カウンセリングや教育の現場でも大きな力を発揮します。
🔁 過去を掘り返すよりも、未来に目を向けて一歩を踏み出す―これがアドラー心理学の姿勢です。
課題の分離と共同体感覚:他者と自分を尊重し合う哲学
アドラー心理学では、「課題の分離」という考え方が非常に有名です。
これは、「誰の課題か」を冷静に見極め、他者の課題には踏み込まず、自分の課題には責任を持つという姿勢です。
たとえば…
- 子どもが勉強しない → 親がイライラしても「勉強するかどうかは子どもの課題」
- 他人にどう思われるか → 「それは相手の課題であって、自分の課題ではない」
このように線引きをすることで、人間関係のストレスや依存から自由になれるのです。
一方で、アドラーは「他者を切り捨てよ」と言っているわけではありません。
むしろ、共同体感覚(社会とのつながりや貢献意識)を育てることが、人間の幸福に欠かせないと説きました。
🌱「自分の人生を生きながら、誰かの役に立っている」―この感覚こそが、アドラー心理学の理想とする生き方です。
勇気づけ:行動変容のベースにあるもの
アドラー心理学の実践の中心にあるのが「勇気づけ」です。
勇気とは、「困難を乗り越える力」のこと。勇気づけとは、その人が「できる」と信じて行動できるように支援することです。
具体的には…
- 「ありがとう」「助かったよ」という承認
- 「やってみよう」「失敗しても大丈夫」といった言葉かけ
- できたことに注目してフィードバックする
これにより、人は自分の価値を感じ、行動を続ける勇気を得るのです。
❌ 一方で、「褒める」は上下関係を生みやすいため、アドラー心理学ではあまり使いません。
💬 代わりに「ありがとう」「頼りにしてるよ」といった“対等な感謝”が、勇気づけの基本です。
- 劣等感は誰もが持っているが、それを補おうとする力が成長の源になる
- ライフスタイルはその人の“人生の意味づけ”であり、無意識に行動を決めている
- 過去ではなく未来の目的に目を向ける「目的論」が行動変容のカギ
- 他者と自分の課題を分けて考えることで、人間関係がラクになる
- 勇気づけは「できるかもしれない」と思える力を人に与える支援の方法
アドラー心理学の基本理論を見てきましたが、こうした考え方は決して「特別な人」のためのものではありません。
むしろ、日常の中でこそ活かされる考え方です。
では、アドラー心理学は、他の有名な心理学(たとえばフロイトやユングの理論)と比べて、どのような違いや共通点があるのでしょうか?
次章では、それぞれの立場の違いをやさしく比較しながら、アドラー心理学の特徴をより鮮明にしていきます🧠⚖️
第三章:アドラー心理学と他の心理学の違いとは?
心理学と一口に言っても、その理論やアプローチはさまざまです。
アドラー心理学もまた、独自の哲学と人間観に基づいた心理学のひとつですが、ほかの有名な理論とはどのように異なるのでしょうか?
この章では、フロイトやユングといった古典的心理学との比較から、行動主義・認知行動療法・ポジティブ心理学まで、アドラーとの違いや共通点を整理します。
そのうえで、アドラー心理学がなぜ「哲学的心理学」と呼ばれるのかを深掘りしていきます🧠✨
フロイトとの違い:過去のトラウマ vs 未来志向の目的論
フロイトとアドラーはともにウィーンで活動していましたが、考え方は大きく異なります。
フロイトは、人の心を「無意識のトラウマや欲求によって支配されるもの」と捉えました。一方、アドラーは“目的志向”の立場をとります。
| 比較項目 | フロイト | アドラー |
|---|---|---|
| 人間の行動の原因 | 無意識・過去のトラウマ | 目的・未来への志向 |
| 重要視する要素 | 性的衝動や抑圧 | 社会性・所属感・勇気 |
| 対象とする問題 | 内面の葛藤やコンプレックス | 現在の行動パターン |
たとえば「対人関係がうまくいかない」という悩みがあった場合、フロイトはその原因を幼少期の体験に求めるのに対し、アドラーは「今の自分は何を避けるためにそうしているのか?」と未来に目を向けます。
🔍アドラー心理学は、「人は変われる存在」という前提に立つ、実践的かつ希望のある理論です。
ユングとの違い:集合的無意識 vs 個人の社会的役割
ユングもまた、フロイトの弟子として出発し、のちに独自の「分析心理学」を展開しました。
彼は“集合的無意識”や“アーキタイプ(元型)”といった神話的・象徴的な世界観を重視しました。一方、アドラーはより現実的・社会的な立場から人間を見つめていました。
| 比較項目 | ユング | アドラー |
|---|---|---|
| 心の中心 | 無意識の普遍的構造 | 社会との関係性と人生の意味づけ |
| キーワード | 元型・個性化・夢分析 | 劣等感・共同体感覚・勇気づけ |
| 目指す方向性 | 自己実現のプロセス | 社会貢献を含めた自己の再構築 |
🌍ユングは“内なる世界”を旅する心理学、アドラーは“社会の中で生きるため”の心理学、と表現されることもあります。
行動主義や認知行動療法との接点と違い
行動主義や、そこから発展した認知行動療法(CBT)は、実践的でエビデンスに基づいた心理学として高く評価されています。アドラー心理学も実践重視ですが、「行動の背景にある“目的”や“人生観”にアプローチする」という点で一線を画します。
| 比較項目 | 認知行動療法 | アドラー心理学 |
|---|---|---|
| 主な焦点 | 認知の歪みと行動習慣 | 価値観・ライフスタイル・課題の分離 |
| 手法 | 思考の再構成・行動実験 | 勇気づけ・ライフスタイルの再構築 |
| セッションの特徴 | 技術的で論理的 | 関係重視・対話的・哲学的要素が強い |
🛠️どちらも「困りごとを解決する」という点では共通しますが、アドラーは“対等な人間関係”と“人生の目的”により強くフォーカスします。
現代のポジティブ心理学との親和性
2000年代以降、ポジティブ心理学(マーティン・セリグマンなど)が注目を集めています。
これは、従来の“問題解決”にとどまらず、“人がよりよく生きるには?”という視点を持った心理学です。実は、アドラー心理学はこのポジティブ心理学と非常に親和性が高いのです。
- 自己決定感(autonomy)
- 貢献感(contribution)
- 意味のある人生(purpose)
これらはすべて、アドラーが100年前から提唱していた「共同体感覚」「ライフスタイル」「目的論」と重なる考え方です。
🌱現代社会における“ウェルビーイング(心の豊かさ)”を考えるうえでも、アドラー心理学は大きなヒントになります。
「哲学的心理学」としての独自性
アドラー心理学は単なる治療技法ではなく、「生きるとはどういうことか?」という根源的な問いに向き合った“哲学的心理学”とも言われます。
- 「人はどんな存在か?」 → 変わる力を持つ、社会的存在
- 「何のために生きるのか?」 → 貢献感・つながり・選択による意味づけ
- 「どう在ればよいか?」 → 自己受容と他者尊重、勇気を持って行動する
これらは、クライアントだけでなく、心理支援に関わる側の“在り方”にも深く関わってきます。
🧩アドラー心理学が現代にも通用するのは、単に理論や技法ではなく、“人間観そのもの”を再定義する力を持っているからなのです。
- フロイト:過去重視・原因論 ⇔ アドラー:未来重視・目的論
- ユング:内的世界重視 ⇔ アドラー:社会的役割・対人関係重視
- 認知行動療法:認知と行動の再構成 ⇔ アドラー:価値観やライフスタイルにアプローチ
- ポジティブ心理学とは重なる部分が多く、アドラーはその先駆けとも言える
- 哲学的視点を持った心理学であり、私たちの“生き方”を支える思想でもある
これまでアドラー心理学の基本や、他の心理学との違いを見てきました。
理論としての深さと同時に、実生活での活用のしやすさもアドラー心理学の魅力です。
では、実際にこの考え方を自分の人生に取り入れていくには、どうしたらよいのでしょうか?
次章では、アドラー心理学を“学び、実践する”ためのステップを、書籍や講座、ワーク例などを交えながらご紹介していきます📘📝
第四章:アドラー心理学が活きる場面とユースケース
アドラー心理学の魅力は、単なる理論にとどまらず、「日常のあらゆる場面で実践できる」点にあります。
自己肯定感を高めたいとき、職場の人間関係に悩んだとき、子育てで迷ったとき──それぞれの場面でアドラーの考え方は、私たちの行動のヒントになってくれます。
この章では、実際にアドラー心理学が活きる5つのユースケースを紹介しながら、どう生活に取り入れられるのかを具体的に解説していきます🧭🌿
自己受容・自己肯定感の育み方(勇気づけの実践)
自己肯定感が低いと感じる人にとって、アドラー心理学は大きな支えになります。
そのカギは「勇気づけ」という関わり方にあります。
勇気づけとは、「あなたには価値がある」「やってみていいんだよ」というメッセージを言葉・態度・関係性で伝えること。
これは、自己受容の土台をつくる上で非常に大切なアプローチです。
例えば…
- ミスをして落ち込む →「失敗しても、挑戦したあなたはすごいね」
- 自分に自信がない →「ここまで頑張ってきた自分に気づいてあげよう」
アドラー心理学では、「人は変わる力を持っている」と信じ、過去の失敗ではなく“これからどうするか”を大切にします。
勇気づけは、自己否定から自分を解放し、“自分で自分を信じる力”を養ってくれます。
人間関係(職場・家庭・学校)における課題の分離
アドラー心理学の代表的な考え方「課題の分離」は、あらゆる人間関係のストレス軽減に効果的です。
✔「相手がどう思うか」は相手の課題
✔「自分がどうふるまうか」は自分の課題
この線引きを意識するだけで、「他人の反応に振り回されない生き方」が可能になります。
たとえば…
- 上司が怒っている →「それは上司の感情。自分が誠実でいられるかが大切」
- 子どもが勉強しない →「やるかどうかは子どもの課題。自分の課題は環境を整えること」
このように、自他の課題を切り分けることは、相手との“健全な心理的距離”を保つのに役立ちます。
🔗課題の分離は、自立と尊重の人間関係をつくる大きなヒントです。
子育てにおけるアドラー心理学(褒めない・叱らない関わり)
「ほめて育てる?それとも叱ってしつける?」──そんな疑問に対し、アドラー心理学はまったく新しい視点を提示します。
それが、「ほめない・叱らない」という関わり方。代わりに用いるのが「勇気づけ」と「協力の関係」です。
たとえば…
✅「すごいね!」ではなく「ありがとう、助かったよ」
✅「何でできないの!」ではなく「どこが難しかったかな?」
このように、「子どもが自分の力でできた」と感じられる声かけや姿勢が、内発的動機づけや責任感を育みます。
また、子どもにも“課題の分離”を伝えることで、自分で考える力が養われ、自立心を支える教育にもつながります。
🏠 子育てにこそ、アドラーの哲学が活きてきます。
カウンセリング・教育・医療での活用事例
アドラー心理学は、心理支援・教育・医療などの対人援助職でも広く取り入れられています。
- カウンセリング:クライエントの「できていること」に注目し、勇気づけをベースに関わる
- 教育現場:生徒との“対等な関係”を築くうえで、勇気づけや課題の分離を活用
- 医療現場:病と向き合う患者さんの「社会的つながり」や「人生の意味づけ」に光を当てる
アドラー心理学は、「その人をどう変えるか」ではなく「その人の力を信じて支える」アプローチです。
それは、専門職の姿勢や在り方そのものを問い直す力を持っています。
経営やリーダーシップにおけるアドラー的視点
近年、経営やマネジメントの分野でも、アドラー心理学が注目されています。
その理由は、「対等な関係」「勇気づけ」「目的志向」という考え方が、心理的安全性や主体性を育むうえで非常に効果的だからです。
具体的には…
- 上司が部下をほめるのではなく、「感謝」と「信頼」を伝える
- 業務命令ではなく、「なぜそれをやるのか?」という目的を共有する
- 成果よりプロセスやチャレンジを評価する文化をつくる
これらは、従来の「コントロール型リーダー」から、「支援型リーダー」への転換を促すヒントにもなります。
💼アドラー心理学は、組織の風土づくりやチームビルディングにも活用できる“人間理解の道しるべ”なのです。
- 勇気づけは、自己肯定感や自己信頼感を高める実践的手法
- 課題の分離は、人間関係のストレスを減らすシンプルで強力な方法
- 子育てにおける「褒めない・叱らない」関わりは、子どもの自立心を育む
- カウンセリングや教育・医療の現場で、信頼と尊重の姿勢を実践できる
- 経営やリーダーシップにも応用可能な、対人関係のベースとなる考え方
アドラー心理学の理論や考え方は、さまざまな場面で実際に活かされています。
しかし、理論を「知る」だけではなく、「使いこなす」ことができてこそ、その本当の価値が発揮されます。
では、アドラー心理学を日常生活の中で学び、深め、実践していくにはどうすればよいのでしょうか?
次章では、初心者でも取り組みやすい学び方や、日常でできる実践のステップをご紹介していきます📘🧩
第五章:アドラー心理学を学び・実践するには?
アドラー心理学の思想に触れて、「もっと深く知りたい」「自分の生活に取り入れたい」と感じた方も多いのではないでしょうか。
アドラー心理学は、特別な人だけのものではなく、誰もが今日から学び、実践できる心理学です。
この章では、初心者におすすめの入門書や学習方法、日常生活での実践例、そして仲間と学び合えるコミュニティなど、アドラー心理学を“続けて深める”ためのステップを紹介していきます📚🕊️
おすすめの入門書・名著
まずは、書籍から学び始めたい方におすすめの本をいくつかご紹介します。
📖『人生の意味の心理学』(アルフレッド・アドラー 著)
アドラー自身の講演録をもとに編集された一冊で、アドラー心理学のエッセンスが詰まっています。難解に感じられる箇所もありますが、原点を知るには欠かせない書です。
📕『嫌われる勇気』(岸見一郎・古賀史健 著)
アドラー心理学の考え方を、対話形式でわかりやすくまとめたベストセラー。若い世代や心理学初心者にも親しみやすい一冊です。
📘『アドラー心理学入門』(岸見一郎 著)
「ライフスタイル」や「共同体感覚」などのキーワードを、より理論的に整理して学べます。
📙そのほか、実践に役立つ本として『愛と勇気づけの子育て』(岩井俊憲 著)などもおすすめです。
カウンセリング現場での応用例
心理カウンセリングやメンタルケアの現場でも、アドラー心理学は有効なアプローチです。
とくに「勇気づけ」や「目的論的な見立て」は、クライエントとの関係づくりにおいて重要です。
カウンセリングでは…
- 過去の出来事を深堀りするより、「今どうしたいか」「どこに向かいたいか」を大切にする
- クライエントの強みや価値を見出し、「変化への意欲」を引き出す関わりを行う
アドラー的アプローチは、「話すことで自分を取り戻す」ことを支える土台にもなります。
日常で実践できる「勇気づけワーク」や「ライフスタイルの見直し」
アドラー心理学を日常で活かすには、ちょっとした習慣や振り返りの時間が役立ちます。
📝【勇気づけの実践ワーク】
| ワーク内容 | 方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 1日1つ、自分を勇気づける言葉をメモする | 「今日は〇〇をやり切れたね」と書き出す | 自己信頼の強化に◎ |
| 他者への「ありがとう」を意識的に伝える | 家族・同僚など、言葉で伝えてみる | 共同体感覚を育てる |
| 自分の「ライフスタイル」を振り返る | 思考の癖・対人傾向を書き出して気づく | 行動の目的に気づき、変容のきっかけに |
🧠 日常の中で少しずつ取り入れることで、「考え方のクセ」や「人との向き合い方」が自然に変化していきます。
学びを深め続けるためのステップとコミュニティ
継続してアドラー心理学を学びたいときは、仲間との学び合いや、実践の場が欠かせません。
🌐【継続学習のためのヒント】
- オンラインのアドラー心理学サロン・勉強会に参加する
- 書籍を読み合い、感想をシェアする“読書会”を開く
- アドラーを学んでいる仲間と、日常での気づきを交換し合う
- 自分自身のカウンセリングやコーチングを通じて、実践と内省を深める
心理学は“知識”ではなく、“関係性”や“実践”のなかで育っていくものです。
アドラー心理学もまた、学びを通じて“他者とのつながり”を感じられる心理学です🤝
- 書籍から学ぶなら『嫌われる勇気』『人生の意味の心理学』が定番
- カウンセリングや教育現場で実践されている信頼性ある心理学
- 日常のなかでできるワーク(勇気づけ・ライフスタイル振り返り)が実践の第一歩
- 学びを深めるには、コミュニティや勉強会に参加して「共に学ぶ」姿勢が大切
アドラー心理学は、単なる“知識”ではなく、“生き方”に根ざした心理学です。
私たちが日常で直面する悩みや葛藤を、「変われる力がある」と信じて支えてくれる力があります。
書籍・ワーク・コミュニティなど、さまざまな入り口から学びを始めることができ、自分らしく、他者とつながりながら生きるための“心の羅針盤”となってくれるでしょう。
ぜひ、あなたらしい一歩から始めてみてください🕊️✨