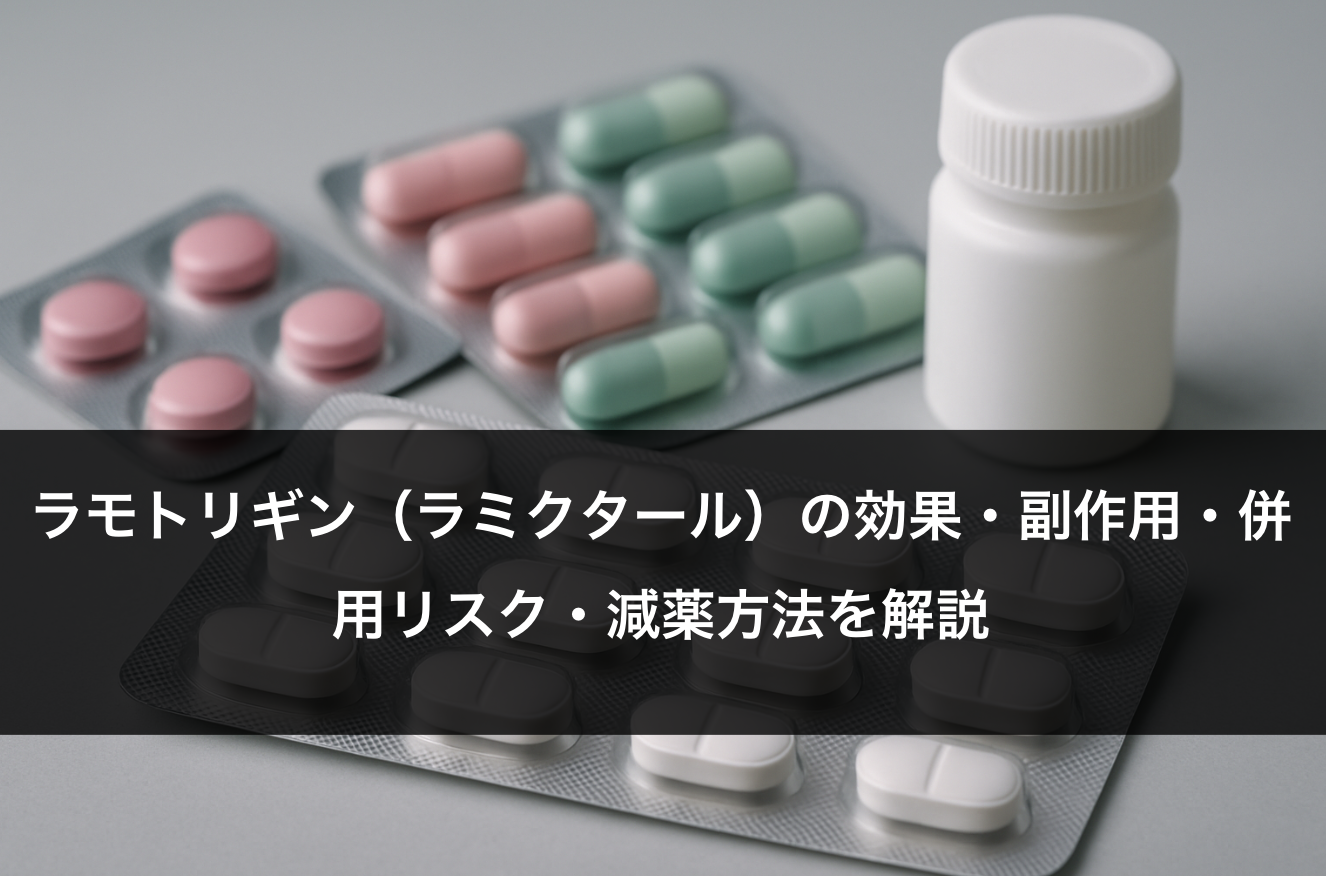ラモトリギンは、双極性障害のうつ状態やてんかんの発作を予防するために用いられる、気分安定薬・抗てんかん薬のひとつです。
この薬には多くの特徴や注意点があり、正しい知識を持つことで安心して治療に取り組むことができます。
そこでこの記事では
- お薬の基本情報
- 適応疾患と効果
- 副作用や飲み合わせの注意点
- 他の気分安定薬との違い
- 減薬の進め方
などを医師監修のもと、わかりやすく丁寧にお伝えします。
※本記事はファクトチェックを徹底しており、青字下線が引いてある文章は信頼できる医学論文への引用リンクとなっています。
ラモトリギン(ラミクタール)とは?基本情報
双極性障害の治療やてんかんの発作予防に使われる「ラモトリギン(商品名:ラミクタール)」は、気分の波を穏やかにする薬として広く使用されています。
この章では、ラモトリギンの基本的な位置づけと、脳内でどのように働くのかを、医学的根拠に基づきながらわかりやすく解説します。
どんな薬?(抗てんかん薬・気分安定薬としての位置づけ)
ラモトリギンは、元来てんかんの治療薬として開発され、現在も「部分発作」や「全般発作(強直間代発作など)」のコントロールに使われています。
その後、双極性障害に対する効果が注目され、気分エピソード再発予防(維持療法)を目的として使われるようになりました。
精神科での適応:双極性障害の維持療法
ラモトリギンは双極性障害の維持療法に適応があり、躁やうつエピソードの再発を抑制する効果が認められています。
国内でも、「双極性障害の再発・再燃抑制」を目的として広く用いられています。
ただし、後述しますが、増量に時間がかかる薬剤であるがゆえに、急性期の躁状態や抑うつ症状に対してはあまり使用されません。
気分安定薬の中でのラモトリギンの特徴
他の気分安定薬(たとえばリチウムやバルプロ酸)は、躁状態のコントロールに強みを持つ一方、ラモトリギンはうつ状態の再発予防に効果を発揮する傾向があります。
そのため、「気分の波がうつ寄りに偏っている方」に対して、治療選択肢として検討されることがあります。
長期的に服用されることが多い
ラモトリギンは、気分が安定した後も「再発防止のための維持療法」として、長期間にわたり継続的に使用されるケースが多い薬です。
再発を繰り返すと、生活や社会的機能に大きな影響を及ぼすため、長期的な予防医療としては極めて重要です。
また、ラモトリギンは比較的副作用が少なく、認知機能や体重への影響も少ないとされており、長期使用においても患者さんの生活の質を保ちやすい点が特徴です。
作用機序(グルタミン酸抑制・気分安定作用)
ラモトリギンが「気分の波」や「てんかん発作」を抑える理由は、脳内での神経活動を落ち着かせる働きにあります。
ラモトリギンの正確な気分安定作用の機序は完全には解明されていませんが、以下の2つの作用が主に関係していると考えられています。
ナトリウムチャネルを抑制して神経を安定させる
ラモトリギンは、「電位依存性ナトリウムチャネル」という神経細胞の興奮を伝える通路の働きを抑えることで、神経の過剰な活動を鎮める効果があります。
これにより、てんかん発作のような異常な電気信号の拡がりを防ぐほか、情動の急激な高ぶりにも影響を与えると考えられています。
興奮性伝達物質(グルタミン酸)の過剰放出を抑える
また、ラモトリギンは、脳内で興奮性の神経伝達物質であるグルタミン酸の過剰な放出を抑える作用も持っています。
グルタミン酸が過剰に分泌されると、気分障害や神経細胞へのダメージ(神経毒性)につながる可能性があり、ラモトリギンはこの点でも気分安定作用を補完していると考えられています。
- ラモトリギンは、もともと抗てんかん薬として開発されたが、現在は双極性障害の維持療法にも使用される
- 適応は双極性障害の再発予防(躁・うつの両方)であり、増量に時間がかかるため急性期治療にはあまり適さない
- ナトリウムチャネル抑制とグルタミン酸放出抑制により、脳の興奮を抑える作用があると考えられている
ラモトリギン(ラミクタール)の適応疾患と効果
この章ではラモトリギンの適応疾患と臨床効果について詳しく解説します。
双極性障害と抑うつの関係、躁状態との相性、さらにはてんかん領域での位置づけまで、最新の診療ガイドラインとともにわかりやすくお伝えします。
利用シーン:双極性障害の抑うつ状態への効果
ラモトリギンは、双極性障害の維持療法(再発予防)として正式に承認されている薬です。
特に抑うつ状態の再発を防ぐ目的で、精神科で広く処方されています。
抑うつ状態が長く続くことが多い場合に使われる
双極性障害では、躁状態や軽躁状態よりも「抑うつ状態」が長引きやすいという特徴があります。
実際の研究でも、抑うつ症状に苦しむ期間は躁状態の期間の約3倍に及ぶとされ、特に双極Ⅱ型障害では抑うつ症状が経過の大部分を占めることも珍しくありません。
このように、気分の落ち込みが慢性化しやすいタイプの方にとって、抑うつエピソードの再発を防ぐことは生活の安定に直結する重要なテーマです。
承認適応は「双極性障害の維持療法」
アメリカの食品薬品局FDAでは、ラモトリギンは双極Ⅰ型障害の気分エピソード(うつ・躁)の再発・再燃を遅らせる維持療法として承認されています。
これは、急性期の症状に対する即効性を目的とするものではなく、「気分の波の再発そのものを減らす」ための使い方です。
急性うつへの効果は「適応外」ながら推奨されることも
一方で、急性のうつエピソードに対する適応は正式には認められていません。
ただし、カナダのCANMATや国際双極性障害学会(ISBD)、イギリスのNICEなど複数の臨床ガイドラインでは、双極性障害の急性期の抑うつ状態に対しても選択肢として推奨されています。
このため、臨床現場では急性期への使用も見られますが、個々の状態や医師の判断によって使い方は異なります。
抑うつ傾向が強い方で検討されやすい
抑うつ状態の再発が多い方、過去に他の薬で副作用が強かった方などでは、ラモトリギンが選択肢に挙がることがあります。
気分の波が「うつ寄り」の方にとって、中長期的な安定化を目指す際に検討される薬のひとつです。
躁状態には効果が乏しい点
ラモトリギンは「うつの再発予防」に強みがありますが、急性の躁状態(躁病エピソード)に対しては効果が乏しいとされています。
急性躁状態には第一選択薬ではない
躁状態とは、多弁、過活動、睡眠欲求の低下、気分の高揚などが強く現れる状態です。
このような急性の躁エピソードに対しては、ラモトリギンは推奨されていません。
そのため、ラモトリギンを服用していても躁状態が出現する場合は、追加で他の薬が処方されるケースが多いのが実情です。
てんかん治療における有効性
記事の冒頭でも述べましたが、ラモトリギンは、もともと抗てんかん薬として開発・承認された薬であり、現在もてんかんのさまざまなタイプに対して広く使われています。
焦点発作や全般発作に有効
ラモトリギンは、以下のようなてんかん発作に対して効果が認められています:
- 焦点発作(旧:部分発作)
- 強直間代発作(全身性のけいれん)
- Lennox–Gastaut症候群(小児に多い難治性てんかん)の全般発作(他の抗てんかん薬との併用療法)
これらの適応は、アメリカFDAをはじめ各国のガイドラインでも正式に承認されており、信頼性の高い治療選択肢とされています。
小児から成人まで適応
ラモトリギンは、小児(2歳未満は慎重投与)から成人まで使用可能であり、特に小児てんかんの中でもLennox–Gastaut症候群の補助療法として有効性が報告されています。
年齢や発作型によって、単剤か併用かが異なるため、専門医の処方が必須です。
- ラモトリギンは双極Ⅰ型障害の維持療法(再発予防)として正式に承認されている
- 急性期に対しては適応外だが、ガイドラインでは選択肢として挙げられている
- 躁状態への効果は乏しく、他薬との併用が必要になることが多い
- てんかん治療(焦点発作・強直間代発作・Lennox–Gastaut症候群)に対する有効性が確立されている
ラモトリギンは多くの方にとって有用な薬である一方、副作用やリスクについて不安を抱える方もいらっしゃるかと思います。
次の章では、ラモトリギンを安全に使うために知っておきたい副作用や注意点、特に重篤な皮膚症状などについて、最新の知見をもとにわかりやすく解説していきます。
ラモトリギン(ラミクタール)の副作用とリスク
ラモトリギン(商品名:ラミクタール)は、双極性障害の抑うつ状態を予防する薬として広く使われていますが、その一方で、特有の副作用にも注意が必要です。
ここでは、よくある軽度の副作用から重篤な皮膚障害のサイン、そして副作用が出やすい時期について、お伝えします。
よくある軽度な副作用(眠気、頭痛、めまい、吐き気など)
ラモトリギンは比較的副作用が少ないとされる薬ではありますが、それでも一定の割合で、以下のような軽度の副作用がみられることがあります。
特に服薬開始初期や増量時には、体が薬に慣れていないために症状が出やすい傾向があります。
主な軽度の副作用
- 眠気(傾眠):日中にボーッとする、集中しづらい
- 頭痛・めまい:頭が重い感じやふらつき
- 吐き気・食欲低下:特に空腹時に気持ち悪さを感じることも
- 不眠または過眠:睡眠リズムが一時的に乱れる
- 倦怠感・だるさ
これらの症状は、通常は数日から1〜2週間程度で自然に軽減していくことが多いです。
もし生活に支障がある場合には、服用時間を夜にする、食後に服薬するなどの工夫で軽減されることもあります。
副作用で困る場合は、主治医としっかり相談しましょう。
対処の工夫
- 吐き気が強いときは、食後に服用することで楽になることがあります。
- 日中の眠気が強い場合は、夜に服用時間をずらすことで改善するケースがあります。
- ふらつきがある場合は、運転や高所作業などは控え、安全を確保しましょう。
また、ラモトリギンは他の気分安定薬(リチウムやバルプロ酸など)と比較して、体重増加や代謝異常が少ないという特徴があります。
副作用の少なさを理由に選ばれるケースもありますが、効果の感じ方や副作用の出方は人によって異なるため、慎重な観察が大切です。
上記のように服用タイミングを変えたいときは、必ず医師に相談しましょう。
重篤な副作用(スティーブンス・ジョンソン症候群などの皮膚症状)
ラモトリギンでもっとも注意すべき副作用は、皮膚に現れる重篤なアレルギー反応です。
中でも「スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)」や「中毒性表皮壊死症(TEN)」はまれながらも重篤な疾患で、生命に関わる危険性があります。
主な重篤な皮膚症状
- 発熱やだるさが数日続く(風邪のような初期症状)
- 赤い発疹やブツブツが身体に広がる
- 口の中や目、性器などの粘膜にただれや痛み
- 水ぶくれや皮がむけるような皮膚変化
これらはSJS/TENの前兆・初期症状である可能性があります。
とくにラモトリギンでは、服薬開始後2〜8週間以内に発症することが多いとされています。
重大な皮膚症状が出た場合の対応
- すぐに服薬を中止し、医師へ相談してください(※自己判断で様子をみるのは極めて危険です)。
- 「発疹が出ても軽いなら続けてよい」という判断は、ラモトリギンでは当てはまりません。
- 特に粘膜を伴う皮疹、発熱を伴う紅斑、痛みが強い水ぶくれなどは赤信号です。
- 軽度の副作用(眠気、頭痛、吐き気など)は一時的なことが多い
- ラモトリギンの最大のリスクは皮膚に現れる重篤なアレルギー反応
- 特にSJS/TENは発熱・発疹・粘膜びらんが特徴で、初期対応が命を守るカギ
- 発熱や口・性器・目の粘膜に痛みを伴う発疹が見られた場合、すぐに医療機関受診する
- 副作用は服薬開始〜2か月以内に集中しやすい
薬について不安を感じたら、セカンドオピニオンを利用する選択肢も

副作用が続いたり、日常生活に影響が出てしまうと、「このまま薬を飲み続けて大丈夫なのかな?」と不安になる方も少なくありません。
実際、多くの患者さんが「副作用は一時的なのか」「別の治療薬はないのか」と悩まれています。
そんな時に役立つのが、セカンドオピニオンという選択肢です。
本メディアMental Care Journalでは
- 自分の症状と薬が合っているのか、不安…
- 薬の副作用がつらいが、主治医に言い出しにくい
- いまの薬を続けるべきか、客観的な意見が欲しい。
といった方に対して精神科医による監修付きのセカンドオピニオンを72時間以内にお届けするサービスを提供しています。
不安を一人で抱え込まずに、安心して次の一歩を考えるための相談先としてご活用ください。
服薬時の注意点 – 飲酒や飲み合わせ、妊娠・授乳時について
ラモトリギン(ラミクタール)を正しく安全に使うためには「用量調整」「飲み合わせ」「妊娠・授乳中の対応」など、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。
この章では、日常の服薬に関わる注意点を具体的に解説していきます。
服用量の増減(ゆっくり増量が必要な理由)
ラモトリギンは、決められたスケジュールに沿ってゆっくりと増量していく必要がある薬です。
これは、先ほど述べた重篤な皮膚障害(スティーブンス・ジョンソン症候群など)の発症リスクを最小限に抑えるためです。
基本的な増量スケジュール(成人/グルクロン酸抱合誘導薬なし・バルプロ酸なし)
- 1〜2週目:25mgを1日1回
- 3〜4週目:50mgを1日1回
- 5週目:100mgを1日1〜2回分割
- 6週目以降:200mgを1日1〜2回分割(維持用量)
これはあくまで一例であり、体格や症状、併用薬の有無(後述)によって調整されます。
飲み忘れたときの対応
飲み忘れは誰にでも起こりうることですが、ラモトリギンは連続服用が非常に重要な薬であり、自己判断での調整は危険です。
飲み忘れに気づいた場合
- 何時間以上経過しているかで対応が変わるため、基本的に医師・薬剤師に相談をしてください。
- 絶対に2回分をまとめて飲まないでください。
5日以上飲み忘れた場合
- 半減期(体内で薬の濃度が半分になる時間)が過ぎると、皮膚症状リスクが再度高まるため、再導入(最初から漸増)が必要になることがあります。
- この場合は、必ず主治医に相談し、安全なスケジュールで再開しましょう。
アルコールや他の薬との飲み合わせ注意点
ラモトリギンは、他の薬やアルコールと相互作用を起こすことがあります。
副作用や効果の変動を避けるためにも、飲み合わせには十分注意が必要です。
アルコールとの併用
- ラモトリギンとアルコールを併用すると、眠気や注意力低下が強くなることがあります。
- 特に服薬初期や増量中は、少量の飲酒でも酔いやすくなることがあるため、控えるか慎重に。
他の薬との相互作用
- バルプロ酸:血中濃度が2倍以上に上昇し、副作用リスクが高まる → 初期用量を半分以下に調整。
- カルバマゼピン、フェニトインなど:酵素誘導作用により、血中濃度が約40%低下 →ラモトリギンの効果が下がるため、用量調整が必要。
- エストロゲン含有経口避妊薬:ラモトリギンの濃度が約50%低下し、休薬週には一時的に2倍程度に上昇する可能性があります。
※プロゲスチン単剤ピルは、ラモトリギンへの影響が少ないとされています。
妊娠中の安全性(催奇形性リスクと比較検討)
ラモトリギンは妊娠中に使われる薬の中では、比較的安全性が高いとされる気分安定薬・抗てんかん薬の一つです。
しかし全くリスクがないわけではないため、妊娠中または妊娠を希望する方は、必ず医師と事前に相談することが大切です。
催奇形性リスク
- 他の抗てんかん薬(特にバルプロ酸)と比較すると、口唇裂や心奇形のリスクが低いとされています。
- 最新の研究では、「明確な奇形のリスク増加は確認されていない」と報告されています。
- ただし、リスクがゼロというわけではありません。妊娠を計画するときや妊娠が発覚したときは必ず医師に相談をしてください。
妊娠中の服薬管理のポイント
- 可能であれば単剤療法かつ最小有効用量での継続が望ましいとされています。
- 妊娠中は体内の代謝が変化し、ラモトリギンの血中濃度が大きく低下することがあります。症状が悪化しないよう、定期的な血中濃度モニタリングと用量調整が必要です。
- 産後には急激に濃度が上昇することもあるため、産前産後のフォローは慎重に行いましょう。
授乳中の母乳移行と注意点
ラモトリギンは母乳中にある程度移行する薬です。
乳児への影響を懸念する声もありますが、現在の研究では、大多数のケースで母乳育児は継続可能とされています。
母乳への移行と乳児血中濃度
- 母体血中の約20〜50%の濃度が乳児に移行することが知られています。
- 特に母親の服用量が150mg/日以下の場合、乳児の血中濃度は検出限界未満になることも多いと報告されています。
乳児への影響と注意すべき症状
- ごくまれに、傾眠(覚醒を維持しづらい状態)・哺乳力低下・体重増加の遅れ・無呼吸発作などが報告されています。
- こうした兆候がある場合には、すぐに小児科医へ相談してください。
- ラモトリギンは決められたスケジュールでゆっくり増量する必要がある
- 飲み忘れ時は医師・薬剤師に内服してよいか確認する、特に5日以上飲み忘れたときは再導入が必要
- バルプロ酸・避妊薬・アルコールなどとの相互作用に注意
- 妊娠中は単剤・最小用量・濃度モニタリングが安全確保のポイント
- 授乳中も乳児の様子を見ながら継続できる可能性がある
次章では、ラモトリギンと他の気分安定薬(リチウムやバルプロ酸など)との違いを詳しく比較します。
それぞれの薬がどんな症状に適しているのか、副作用の傾向や注意点とともに理解を深めていきましょう。
ラモトリギン(ラミクタール)と他の気分安定薬との比較
気分安定薬には、ラモトリギン(商品名:ラミクタール)以外にも、リチウム(炭酸リチウム)、バルプロ酸(デパケン)、カルバマゼピン(テグレトール)などの選択肢があります。
この章では、ラモトリギンと他の代表的な気分安定薬を比較しながら、それぞれの特徴を解説していきます。
まずは気分安定薬を比較表でざっくり理解
| 特徴項目 | 炭酸リチウム(リーマス) | バルプロ酸(デパケン等) | ラモトリギン(ラミクタール) |
|---|---|---|---|
| 主な適応 | 躁状態・維持療法(再発予防)・自殺予防の可能性(観察研究で有望) | 急性期躁状態・維持療法 | 双極うつの再発予防(維持で有効) |
| 躁状態への効果 | ◎(第一選択) | ◎(第一選択) | ×〜△(急性期躁状態には推奨されない) |
| うつ状態への効果 | ○(維持で再発予防に有効/ガイドラインにより推奨度差あり) | △(単剤の位置づけは限定的) | ◎(抑うつ予防・改善に有効、維持で効果) |
| 自殺予防効果 | ○(観察研究で低減示唆/RCTでは確証不十分) | △(明確な証拠なし) | △(証拠不十分) |
| 血中濃度のモニタリング | 必須(治療域が狭く厳密/腎・甲状腺・電解質も定期に要検査) | 必須(目安50–125 μg/mL/肝機能・血小板も定期に要検査) | 原則不要(ルーチンTDM不要/相互作用時は要検討) |
| 推奨される場面 | 総合的な再発予防・自殺リスクが強い場合の有力候補 | 急性期躁状態、混合状態やラピッドサイクルで状況により選択肢(第二選択〜) | 抑うつ症状が中心のとき・妊娠計画時の有力候補 |
リチウムとの違い(躁状態への効果 vs. 抑うつ状態への効果)
リチウムは、双極性障害の治療薬の中でも歴史が長く、世界中の診療ガイドラインで「第一選択薬の一つ」として位置づけられています。
一方で、ラモトリギンは抑うつ状態への再発予防を目的として使われることが多く、急性期の躁状態に対しては明確な効果がないとされ、単剤での使用は推奨されません。
双極性障害のうつ相(抑うつエピソード)は長く続きやすく、生活に大きな影響を与えるため、再発を防ぐ薬としてラモトリギンが用いられることがあります。
また、リチウムには自殺リスクを減らす可能性があることが観察研究などで示唆されていますが、ラモトリギンではこの点について明確なエビデンスは得られていません。
したがって、自殺リスクが高い患者さんにはリチウムが選ばれることが多くあります。
バルプロ酸との違い(副作用の傾向、妊娠時のリスクなど)
バルプロ酸(デパケン)も、もともと抗てんかん薬として開発されましたが、双極性障害の急性期の躁状態や混合状態に対しても有効性が確認されており、リチウムと並ぶ主要な気分安定薬の一つです。
ラモトリギンが抑うつ状態の再発予防を目的とするのに対し、バルプロ酸は急性期の躁状態や衝動性が強いエピソードでの使用が中心です。
一方で抑うつ状態に対する効果は限定的で、ラモトリギンとは異なる役割を持っています。
さらに、非常に重要なのが妊娠時の催奇形性リスクです。
バルプロ酸は胎児に対して神経管閉鎖障害(例:二分脊椎)や認知発達への影響などのリスクがあることが知られており、欧州などでは妊娠中の使用は原則として禁忌となっています。
- リチウムは躁状態と再発予防に効果があり、自殺リスク低下も期待される
- ラモトリギンは抑うつ状態の再発予防に有効で、急性期躁状態には効果が乏しい
- バルプロ酸は躁状態や混合状態に有効だが、妊娠中は原則禁忌
- ラモトリギンは副作用が比較的少なく、妊娠希望者にも検討されることがある
ラモトリギン(ラミクタール)を辞めたいと思った時の減薬・中止の進め方
ラモトリギンの服用を中止する際には、発作や気分症状の再発といったリスクが伴います。
安全に減薬・中止するためには、必ず主治医と計画を立てながら、段階的に進めることが大切です。
この章では、中止にともなうリスクと、医師と進めるべき減薬スケジュールの考え方について解説します。
急にやめてはいけない理由(発作や再発リスク)
てんかん発作のリスク
ラモトリギンを急に中止すると、脳の興奮を抑える作用が急激に失われ、再発や新たな発作を誘発するリスクが高まることが知られています。
特に過去に強い発作を起こした経験がある方では、中止直後1〜6か月以内に再発するケースが報告されており、運転中・入浴中などに発作を起こすと生命にかかわる危険性もあります。
ラモトリギンを減薬・中止する場合は、てんかん診療のガイドラインに則り、最低2週間以上をかけて徐々に量を減らしていく必要があります。
また、減薬や中止のタイミングでは、運転や高所作業などの活動を一時的に制限することが推奨される場合もあるため、必ず主治医に確認しながら進めましょう。
双極性障害の抑うつ症状再発
双極性障害の維持療法において、ラモトリギンは抑うつエピソードの再発を防ぐことに有効な薬です。
そのため、安定していた気分が、服薬の中止によって崩れるリスクがあります。
NICEガイドラインでは、双極性障害の維持療法でラモトリギンを使用している場合、中止時は少なくとも4週間かけて漸減するよう推奨されています。
再発した抑うつ症状は、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失だけでなく、意欲の著しい低下や希死念慮につながることもあります。
こうした症状が再発すると、通院や服薬の継続すら難しくなってしまうため、「よくなってきたからやめる」のではなく、医師の判断のもとで慎重に進めることが必要不可欠です
医師と相談しながらの減薬スケジュール
■ 適応に応じた減薬の進め方
ラモトリギンの減薬方法は、その薬が使われている病気(てんかんか双極性障害か)によって異なるため、医師と内服目的を明確にした上でスケジュールを立てていく必要があります。
- てんかんの場合:FDAの添付文書では、少なくとも2週間かけて段階的に中止するよう記載されており、一般的には週に約50%ずつ用量を減らしていく形が目安とされます。
- 双極性障害の維持療法の場合:NICEガイドラインでは、最低4週間以上かけて漸減することで気分エピソードの再発を防ぐことが推奨されています。
このように、「2〜4週間以上をかけてゆっくりと減薬する」ことが共通した安全策です。
ただし、用量や服薬歴、体調によって柔軟に調整が必要なため、自己判断でのスケジュール設定は避けましょう。
■ 減薬中に実践すべきセルフケア
- 気分や体調の記録をつける
→ 日記やアプリを使って「眠れたか」「落ち込みがないか」などを記録すると、再発の兆しを早期に察知できます。 - 家族・支援者と早期警戒サインを共有する
→ 気分の変化や言動の異変に気づいてもらうために、「どんなときに注意が必要か」をあらかじめ伝えておきましょう。 - 異変があればすぐに受診
→ 減薬中に不眠・強い不安・意欲低下などが現れた場合、再発のサインかもしれません。無理せず医師に相談してください。 - 焦らず進めることを大切に
→ 「あと少しだから一気にやめよう」と思ってしまうのは自然なことですが、無理な中止は逆効果になり得ます。ゆっくり確実に減らしていくことが、最終的な減薬成功への最短ルートです。
- ラモトリギンは急にやめると発作や抑うつ症状の再発リスクがある
- てんかんでは2週間以上、双極性障害では4週間以上かけて段階的に減薬
- 離脱症状は少ないが、不安・不眠・情緒不安定が出る場合もある
- 併用薬とのバランスを崩さないように、医師と慎重に計画を立てる
- 減薬中は気分の記録・家族との共有・早めの受診・焦らない姿勢が重要
薬について不安を感じたら、セカンドオピニオンを利用する選択肢も

副作用が続いたり、日常生活に影響が出てしまうと、「このまま薬を飲み続けて大丈夫なのかな?」と不安になる方も少なくありません。
実際、多くの患者さんが「副作用は一時的なのか」「別の治療薬はないのか」と悩まれています。
そんな時に役立つのが、セカンドオピニオンという選択肢です。
本メディアMental Care Journalでは
- 自分の症状と薬が合っているのか、不安…
- 薬の副作用がつらいが、主治医に言い出しにくい
- いまの薬を続けるべきか、客観的な意見が欲しい。
といった方に対して精神科医による監修付きのセカンドオピニオンを72時間以内にお届けするサービスを提供しています。
不安を一人で抱え込まずに、安心して次の一歩を考えるための相談先としてご活用ください。
まとめ
ここまで、ラモトリギンについて幅広くご紹介してきました。
この薬は「うつ状態の再発予防」や「てんかんの発作コントロール」においてとても大切な役割を担っていますが、薬の特性や注意点を理解しておくことで、より安心して治療に臨むことができます。
また、服薬中の不安や疑問は、我慢せず主治医や薬剤師を始め、医療者に相談することが大切です。
「聞いてもいいのかな…」と思ってしまうような些細なことでも、しっかり医療者に相談をすることで、あなたの安心につながります。
最後に、本記事のポイントを以下にまとめます。
- ラモトリギンは、双極性障害の抑うつ状態やてんかんの発作予防に使われる薬です
- 副作用は比較的少なめですが、重篤な皮膚症状には注意が必要です
- リチウムやバルプロ酸とは得意分野が異なり、使い分けが重要です
- 妊娠希望の方には安全性が高いとされることがあります
- 減薬・中止は医師と相談し、2〜4週間以上かけて段階的に行うことが原則です
- 自己判断せず、不安なことや状態変化があれば、すぐに医療者に相談することが大切です
治療はひとりで抱え込むものではありません。
薬との付き合い方を知ることで、より前向きに、自分らしく過ごせる時間が増えていきます。あなたの回復と安定を、心から応援しています。
監修医プロフィール
監修:小林玲美子 先生

【保有資格】 精神科専門医 / 精神保健指定医 / 日本医師会認定産業医
【経歴・実績】 東京大学法学部を卒業後、アパレル企業にて店舗責任者を経験。その後、医学の道へ転身し、国立大学医学部附属病院にて「ベスト研修医」を受賞。
大学病院、児童相談所、行政機関など幅広い現場で、延べ13,000名以上の診療・治療に従事。
現在は自身のクリニックで診療を行う傍ら、30社以上の顧問医・産業医として企業の健康経営を支援している。
実臨床と社会活動の両面から、「真に必要な治療と医療情報」を届けることを大切にし、女性のライフデザイン支援や企業向けキャリアアップ研修の講師としても活動。