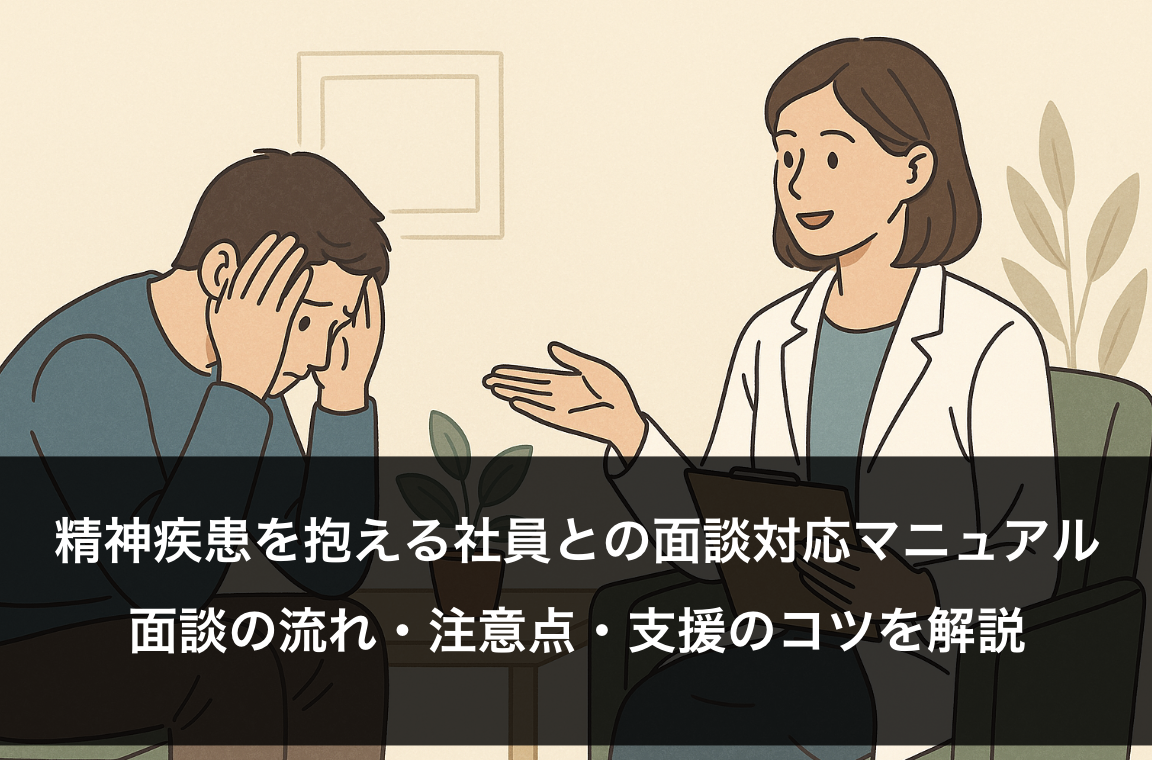「精神疾患のある方との面談…どう向き合えばいいのだろう」――そんな不安や戸惑いを感じている人事担当の方も少なくありません。
何を聞いてよくて、何に気をつけるべきか。どう言葉をかければ、相手を傷つけず、信頼関係を築けるのか。
本記事では、精神疾患を抱える方との面談において、実務的な流れや注意点、心がけたい姿勢について、わかりやすく丁寧にお伝えします。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、相手の立場に寄り添いながら対話する“まなざし”です。
精神疾患を抱える人との面談とは?目的と意義を理解する
精神疾患のある方と面談を行う立場になると、多くの人事担当者が「どこまで踏み込んでいいのか」「言葉選びで傷つけてしまわないか」と不安を抱えるものです。
ですが、そもそもその“面談”が、何のために行われるのかという目的や種類ごとの役割を理解できていないと、不安や迷いが大きくなるのも当然です。
この章では、面談の種類ごとの違いや、それぞれが担うべき意義について、人事の視点から整理していきましょう。
採用面談・定着支援面談・復職面談などの違い
「精神疾患人材との面談」と一口に言っても、その内容や目的は大きく異なります。
人事が関わる主な面談は、次の3つに分類されます。
| 面談の種類 | 主な対象者 | 面談の目的 | 主な確認事項 |
|---|---|---|---|
| 採用面談 | 新規応募者(オープン就労含む) | 業務適性・配慮事項の確認 | 現在の健康状態、希望する配慮、職務の遂行可能性 |
| 定着支援面談 | 入社後間もない社員/既存社員 | 安定就業の継続支援 | 状況把握、支援内容の見直し、体調変化の確認 |
| 復職面談 | 休職からの復帰予定者 | 復職判断と調整 | 主治医の意見、復帰条件、リワーク支援の有無 |
たとえば、採用面談では「診断名の開示」は求めないことが原則です。
障害者雇用の場合を除けば、応募者の健康状態について過度に踏み込むことは、個人情報保護・合理的配慮義務の観点からも避けるべきです。
そして、意外と見落とされがちなのが「定着支援面談」です。
入社直後の定着率が最も低下しやすい精神疾患人材にとって、ここのケアの有無が離職率に直結します。
人事と本人との1on1や、上司との3者面談を計画的に行うことで、早期の問題発見と調整が可能になります。
面談の目的は「評価」ではなく「支援と調整」
精神疾患を抱える方との面談において、しばしば見られる誤解のひとつに、「パフォーマンスが低下している原因を探る場」「業務遂行能力を判断する場」として位置づけてしまうことがあります。
もちろん、仕事との適合性を見極める観点は必要です。
しかしそれは“評価”という一方通行の視点ではなく、支援のための対話、そして環境との“すり合わせ”のプロセスとして捉えることが重要です。
一方的な評価ではなく、「協働による調整」を重視する
たとえば、「最近報連相が減ってきた」「作業の精度が落ちている」といった変化があったとき、面談を通じてそれを“是正する”ことが目的になると、どうしても本人にとっては防衛的にならざるを得ません。
しかし、本来この場で目指すべきは、「何か体調面での変化や、業務の中に負担になっている部分がないか」を一緒に見つけていくことです。
つまり、面談は「問題点を指摘するための場」ではなく、「お互いの立場から率直に話し合い、必要な調整策を共に探る場」であるという認識を、関係者全員が共有する必要があります。
このような面談の在り方を支えるためには、以下のような3つの支援要素が不可欠です。
面談における支援の3要素:「関係構築」「状態把握」「環境調整」
| 支援要素 | 面談時の具体的対応 |
|---|---|
| 関係構築 | 傾聴を基本とし、否定や過度な評価を避ける。 沈黙も受け入れ、安心感を醸成する。 例:「今日は話しにくいことがあれば、無理に言わなくても大丈夫ですよ」 |
| 状態把握 | 通院・服薬の有無、日常生活での困難、職場内でのストレス因子など、本人のペースに合わせて丁寧に確認する。 例:「最近の睡眠や食事のリズムはどうですか?」 |
| 環境調整 | 業務量や配分、勤務形態(在宅・時短など)、報連相の頻度、通勤の負担感など、調整可能な項目をリストアップし、優先順位を本人と一緒に検討する。 |
このように整理することで、面談が“その場しのぎ”の対応ではなく、組織として継続可能な支援体制の起点として機能します。
実際、定着率が高い企業では、本人の調子に合わせて「業務の一部を切り出す」「会議参加はチャットのみ可とする」「繁忙期は業務量を半分にする」といったきめ細かな環境調整を柔軟に実施しているケースが見受けられます。
調整にはもちろん限界もあります。
人手や業務内容の都合で、すべてに応じることは難しいかもしれません。
しかし、その前段として重要なのは、本人との信頼関係のなかで、「話しても大丈夫」「一緒に考えてくれる」という心理的な土壌を育むことです。
調整が必要か否かの前に、「困っていることを言語化し、共有できる関係性」がなければ、適切な支援にはつながりません。
メンタルヘルスの特性理解が、支援と調整の出発点
精神疾患は、外見では分かりづらく、かつ状態の波が大きいという特徴があります。
たとえば、前日は元気に見えていたのに、翌日には無断欠勤――。
こうした一見「理解しがたい行動」も、実は睡眠障害や抗うつ薬の副作用、急激な気分の落ち込みといった背景が隠れていることがあります。
このような変動性を前提とした支援を設計するには、「病名」や「診断」にとらわれすぎず、その人が“今どんな状態にあるか”を丁寧に見ていく姿勢が求められます。
診断名ではなく、体調のリズムや負荷のかかる場面、調子の良い時間帯などに注目することで、より現実的な支援が可能になります。
- 精神疾患との面談は、目的によって「採用」「定着」「復職」の3つに大別される
- 定着面談は離職リスクを下げるカギとなる
- 面談は「評価」ではなく「支援と調整」の場として捉える。
- 関係構築・状態把握・環境調整が支援の3本柱
面談の目的や役割が明確になったとしても、実際の場面では「どこまで聞いていいのか」「どう振る舞うべきか」で迷うことが多いものです。
次章では、精神疾患を抱える方との面談において、特に人事や面接官が気をつけるべきポイント、避けるべき表現や振る舞いについて、具体例を交えて詳しく解説していきます。
精神疾患人材との面談で気をつけること・注意点
面談の目的や種類を理解したうえで、次に押さえておきたいのが「具体的な注意点」です。
精神疾患のある方との面談は、一般的な面談と同じスタンスではうまくいかないことがあります。
無意識のひと言が大きなストレスになったり、逆に気を使いすぎて肝心な情報が得られなかったり――。
この章では、人事や上司として心得ておくべき「配慮の視点」や「避けるべき言動」について、よくある疾患特性を踏まえながら具体的に整理していきます。
疾患特性への理解をもつ(うつ病・双極性障害・不安障害など)
精神疾患を抱える方との面談において、まず大前提として持っておくべき視点が「相手の状態は“外から見えにくい”ことが多い」という理解です。
たとえば身体のケガであれば目に見えますが、メンタルの不調は外見からでは判断できません。
さらに言えば、同じ疾患名であっても、症状の現れ方や生活への影響は人それぞれ異なります。
面談をする担当者として、すべての疾患を医療的に深く理解する必要はありません。
ただし、面談における“見立てのズレ”や“配慮の欠如”による関係の悪化を避けるためには、最低限の疾患理解と、評価しない姿勢が不可欠です。
以下に、人事面談でよく遭遇する代表的な疾患の特性と、その際の配慮ポイントを簡潔に整理しました。
| 疾患名 | 主な特性 | 面談時の配慮ポイント |
|---|---|---|
| うつ病 | ・意欲・集中力の低下 ・自己否定感、身体症状(疲労感、睡眠障害など) | 否定的な言葉に敏感。「励まし」よりも「共感」が有効。「何が負担になっているか」に焦点を当てる |
| 双極性障害(II型含む) | ・気分の波(軽躁状態と抑うつ状態の交互) ・エネルギー量の変動、自覚の乏しさ | 軽躁状態では過活動・自己過信に注意。 抑うつ期とのギャップに戸惑わず、状態の波を前提に話す |
| 不安障害(社交不安障害など) | 強い緊張、対人場面の回避、発汗や動悸などの身体症状 | 「話しにくそう」「目を合わせない」などを“やる気のなさ”と誤解しない。 安心できる環境設定を |
| パニック障害 | 突発的なパニック発作(動悸・過呼吸・めまい)、外出困難 | 面談は予告性・時間制を重視。 本人の体調次第で「中断可能」「リモート選択可」などの配慮も |
誤解を防ぐために:評価基準を“健康な人”に置かない
たとえば、面談中に目を合わせない、返答に時間がかかる、声が小さい――。
これらの行動を「やる気がない」「非協力的」と判断してしまうと、相手はますます口を閉ざしてしまいます。
不安障害やうつ病の方にとって、会話そのものが緊張や負担になっていることもあるため、行動を“症状の一部”と理解する視点が必要です。
また、集中力が続かない、表情が乏しいといった特性も、睡眠障害や服薬による副作用などが関係している可能性があります。
「できない理由」に焦点を当てるのではなく、「どうすればできるようになるか」という支援的な視点を持ちましょう。
「調子が良さそう」は“完治”ではない
特に双極性障害の場合、「今日は元気そうだな」と感じても、それが“本来の安定した状態”とは限りません。
むしろ、軽躁状態のときは周囲よりエネルギッシュで積極的に見えることもありますが、その直後に気分が落ち込み、一気に業務遂行が困難になるケースもあります。
「昨日はあんなに元気だったのに」というギャップこそが、精神疾患特有の波であることを、人事・上司ともに理解しておくことが大切です。
「診断名」よりも「現在の状態」を正しく捉える
精神疾患との関わりにおいて、もうひとつ見落とされがちなのが、“病名だけで本人の状態を判断してしまう”ことへの注意です。
たとえば、「うつ病」と診断されていても、ある人は日常生活を自立して送れる一方、別の人は寝たきりに近い状態で、ほとんど外出もできないかもしれません。
つまり、「同じ病名=同じ状態」ではないという前提を持つことが、適切な面談対応につながります。
また、診断名そのものは本人が自発的に開示しない限り、企業側が把握を強要することはできませんし、してはならないという倫理的・法的配慮もあります。
状態を把握するための質問例
診断名ではなく、“今の生活や仕事にどんな影響があるのか”という観点で、下記のような質問を投げかけてみてください。
- 「朝はどのくらいの時間に起きられていますか?」
- 「1週間のうち、外出できるのは何日くらいですか?」
- 「集中力が保てるのは、だいたいどのくらいの時間ですか?」
- 「体調が安定しやすい時間帯などはありますか?」
これらの質問は、医療的な深掘りではなく、“業務の設計”や“配慮のヒント”を得るための対話として非常に有効です。
回復の波を前提にした設計が必要
精神疾患には、急激な波があります。
昨日までは調子よく出社していたのに、翌日には連絡が取れない――。
このような“突然の落ち込み”に備えて、「いつ」「どんなときに」「どう変化が出る可能性があるか」を、できる範囲で共有しておくと、緊急時の対応もスムーズになります。
面談では、「今の状態」だけでなく、「波の傾向」や「不調時の兆候」も尋ねてみましょう。
「頑張れ」「前はできていた」はNGワード――言葉の選び方が信頼関係を左右する
精神疾患を抱える方との面談では、“何を話すか”と同じくらい、“どう伝えるか”が重要です。
特に注意が必要なのが、励ましのつもりで使った言葉が、相手にとっては大きなプレッシャーや自己否定感につながるケースです。
無意識に相手を傷つけるNGフレーズとは?
以下のような言葉は、意図せずとも相手を追い詰めてしまうリスクがあります。
- 「頑張れ」
- 「前はできてたよね?」
- 「他の人も同じ状況でもやってるよ」
- 「それって甘えてない?」
- 「もっと前向きに考えてみたらどう?」
これらの言葉には、「努力が足りないのでは?」「気の持ちようでは?」というメッセージが含まれており、“原因はあなたにある”という印象を無意識に与えてしまいます。
とくに、精神的に不安定な状態のときは、自責感が強まりやすく、ほんの一言でも「否定された」「見放された」と感じやすくなります。
その結果、面談での信頼関係が損なわれ、以降の対話が困難になる可能性もあります。
「頑張っているのにできない」――見えない努力を尊重する視点を
精神疾患を抱えている方の多くは、表面的には分かりにくくても、自分なりに“すでに頑張っている”状態にあります。
たとえば、うつ病の方は、起き上がるだけでエネルギーを使い果たしていることがあります。
双極性障害の方は、自分の気分の波と格闘しながら、できるだけ普段通りに仕事に向かおうと努力しています。
こうした背景を理解せず、「もっと頑張って」と言われたとき、本人は「これ以上、何を頑張ればいいのか…」と、自責と無力感に陥ることがあります。
つまり、“励まし”のつもりの言葉が、心のシャッターを下ろす引き金になってしまうのです。
安心感と尊重を伝える代替フレーズ
面談時には、本人の努力を前提に、“一緒に考える・支える”という立場を表す言葉が効果的です。
| NGワード | 代わりに使える表現 |
|---|---|
| 「頑張れ」 | 「無理のない範囲でやっていきましょう」 |
| 「前はできてたでしょ?」 | 「今の状況では何が一番負担ですか?」 |
| 「他の人もやってるよ」 | 「あなたにとって、やりやすい方法を一緒に考えたいです」 |
| 「甘えじゃないの?」 | 「つらいと感じていることに、意味があると思いますよ」 |
こうした言葉は、「できない理由を責める」のではなく、「今の状態を出発点として一緒に工夫する」というスタンスを伝えることができます。
“対等な関係性”と“回復の伴走者”という姿勢を言葉で表現することが、面談の信頼構築に直結します。
沈黙や混乱も「当然の反応」として受けとめる
精神疾患のある方との面談では、思うように会話が進まないことを想定しておくことも極めて重要です。
沈黙が続く、質問に答えられない、突然涙を流す――。
これらは決して「話したくない」「ふざけている」のではなく、「言葉が出てこない」「頭の中が整理できない」「不安でいっぱい」という状態の現れです。
たとえば、うつ状態では思考力が著しく低下することがありますし、不安障害では人と向き合うだけで過度な緊張が起こることがあります。
面談が“進まない”=“失敗”ではない
面談の目的は、あくまで「話を進めること」ではなく、「安心して話せる場をつくること」です。
沈黙も含めて、その人の今の状態を受けとめる時間と考えることで、相手との信頼関係はむしろ深まります。
混乱時の対応チェックリスト(人事用)
| 状況 | 具体的な対応策 |
|---|---|
| 沈黙が長く続く | 焦って言葉で埋めようとせず、「急がなくて大丈夫ですよ」と伝える |
| 返答が曖昧/混乱している | 「はい・いいえ」で答えられる質問に切り替える |
| 感情が高ぶる/涙を流す | 「今日はここで一度区切りましょうか?」と中断の提案をする |
| 話しづらそうな様子 | 「同席できる支援者(上司・支援機関)はいますか?」と聞いてみる |
| 面談の緊張が強い | 次回以降はオンライン、短時間などの形に変更することも検討 |
事前準備で不安を軽減できる
実は、こうした混乱や沈黙は、事前の情報提供によって一定程度軽減することが可能です。
- 面談の目的
- 話す予定の内容(例:「最近の働きやすさについてお聞きしたい」)
- 所要時間の目安
- 面談後にどう使うか(記録の取り扱いなど)
これらをあらかじめメールや書面で本人に伝えておくことで、「不意打ち感」や「緊張の高まり」を和らげることができます。
本人の不安を想像し、少しでも「見通しの立つ場」を用意することが、心理的安全性の確保につながります。
- 精神疾患のある方との面談では、疾患ごとの特性を理解しておくことが重要
- 診断名よりも「今の状態」「波の傾向」に注目すべき
- 「頑張れ」はNGワード。共感と肯定的な言葉かけを意識
- 沈黙や混乱も想定内。焦らず対応し、本人のペースを尊重する
- 事前に面談内容や目的を伝えることが、安心感を生む
ここまでで、精神疾患を抱える人材との面談において、どのような配慮や言動が必要かを具体的に整理しました。
しかし、「では実際にどうやって面談を進めればいいのか?」という点については、まだ不安が残るかもしれません。
次章では、当日の面談フローや時間配分、具体的な質問例など、「すぐに使える進め方のテンプレート」をご紹介していきます。
精神疾患人材との面談の流れと進め方
精神疾患を抱える方との面談は、「共感」や「配慮」が重要である一方で、曖昧なまま進めてしまうと「何をどう話せばいいか分からない」「聞きたいことが聞けなかった」という事態にも陥りがちです。
面談が形式的なものに終わってしまえば、本人にとっても企業にとっても意味のある支援にはつながりません。
この章では、面談の事前準備から実施、実施後の対応までを3ステップで整理し、安心して臨める流れを具体的にご案内します。
事前準備(配慮事項の確認・面談目的の明確化)
先ほども述べましたが、面談をスムーズかつ有意義にするには、「何を確認し、どこまで話すか」を事前に明確にしておくことが最重要ポイントです。
準備段階で抜け漏れがあると、当日慌てるだけでなく、相手に不信感を与えることにもつながります。
チェック1:本人の配慮事項・希望の把握
面談の前に、下記のような情報を関係者間で確認しておきましょう。
- 本人から過去に申し出のあった配慮内容
- 主治医や就労支援機関の意見(※本人同意がある場合)
- 上司・現場チームからのフィードバック(困りごと、気になる変化など)
これらをもとに、面談の目的を絞り込むことが鍵です。
目的が曖昧なまま話し始めると、単なる雑談で終わってしまうリスクが高まります。
チェック2:本人にも目的と概要を事前共有
本人に対しては、「今回の面談の目的」「聞きたいこと」「所要時間」などを事前に伝えておくことが必須です。
例)
- 「体調面を踏まえた働き方をすり合わせたい」
- 「今後の業務調整について相談したい」
- 「支援体制の見直しに向けてヒアリングをしたい」
こうすることで、本人が過度に緊張せず、「準備して臨める」状況を作ることができます。
当日の進行(時間配分・話し方・質問例)
面談当日は、「限られた時間内でどこまで話を深めるか」が鍵になります。
人事が一方的に話すのではなく、“安心して話せる雰囲気づくり”と“整理された進行”のバランスが求められます。
推奨される進行フロー(30〜45分を想定)
| フェーズ | 目安時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 導入 | 5分 | 目的と趣旨の説明、安心感を伝える言葉かけ |
| 状態把握 | 10〜15分 | 現在の体調・困っていること・業務の負担感など |
| 調整相談 | 10〜15分 | 可能な配慮・業務改善・連携のすり合わせ |
| まとめ | 5〜10分 | 合意事項の確認、次回フォローの案内など |
話し方の工夫ポイント
- 「どうですか?」よりも「最近は朝、起きやすいですか?」など具体的に
- 沈黙は待つ(焦って言葉で埋めない)
- 「話しにくければ、後日メールでも構いません」と逃げ道をつくる
- メモを取る際は「大切なことなので、メモさせてください」と一言添える
よく使われる質問例
| 聞きたいこと | 質問例 |
|---|---|
| 体調の安定度 | 「波はありますか?どんなタイミングで変動しやすいですか?」 |
| 業務への影響 | 「最近の業務で負担を感じていることはありますか?」 |
| 周囲との関係性 | 「チームメンバーとのやりとりで気になることはありますか?」 |
| 希望の働き方 | 「今の勤務ペースはご自身としてどう感じていますか?」 |
目的は“評価”ではなく“支援”であることを忘れずに。
話の内容よりも、信頼関係の構築が面談全体の成果を大きく左右します。
面談後の対応(記録、関係部署との連携、支援体制の整備)
面談を行って終わり――では意味がありません。
むしろ面談後のアクションこそが、「面談が効果的だったかどうか」を左右します。
ポイント1:記録を残す
- 誰が・いつ・どのような目的で面談を行ったか
- 本人の発言内容、すり合わせた事項
- 今後の対応方針とフォロー予定
これらを記録に残すことで、トラブル予防・業務引き継ぎ・本人との認識ズレ回避に役立ちます。
なお、本人のプライバシーに配慮した記録管理(アクセス権限制限等)も必須です。
ポイント2:関係者との連携
- 現場上司へのフィードバック(※本人の同意を得たうえで)
- 産業医や保健師との連携が必要な場合は、相談タイミングを明確に
- 障害者雇用の場合は、定着支援事業者やジョブコーチとの情報共有も
特に、「言った・言わない」のすれ違いを防ぐためには、人事・上司・産業医間の連携体制づくりが鍵です。
ポイント3:支援体制を可視化・共有
支援策は、実行されなければ意味がありません。
たとえば、以下のような項目を「支援プラン」として見える化し、本人や上司と共有することで、職場内の支援力が高まります。
| 支援内容 | 担当者 | 実施期限 | 確認方法 |
|---|---|---|---|
| 業務量の段階的な調整 | 上司 | ◯月末まで | 面談時に確認 |
| 通院に伴う勤務調整 | 人事 | 随時 | 月次勤務表で確認 |
| メンタル不調時の報連相ルート明確化 | 人事 | ◯月◯日まで | Slack等で共有 |
- 面談前には目的・確認事項・本人への事前説明を整理しておく
- 面談当日は30〜45分を目安に、導入→状態把握→調整→まとめの流れで進行
- 質問は具体的に、本人のペースを尊重しながら話す
- 面談後は記録を残し、関係者との連携・支援策の可視化を行う
- 一度の面談で完結させず、「継続的な支援の起点」として設計する
面談の設計から実施、実施後のアクションまで、一連の流れを具体的に見てきました。
しかし、面談は一方向の対応ではなく、職場全体の「支援体制」や「リスクマネジメント」の一部でもあります。
次章では、より制度的・組織的な対応として、主治医や支援機関との連携をどう進めるか、法的な留意点や実務上の工夫について深掘りしていきます。
主治医・就労支援機関との連携の重要性
精神疾患を抱える方への職場支援において、面談の質を高めることはもちろん重要です。
しかし、それだけでは支援体制として不十分なことも少なくありません。
とくに、症状の把握や回復段階の見極め、支援方法の調整などを行う場面では、医療機関や福祉機関との連携が不可欠です。
情報共有の大前提は「本人の同意」
まず大前提として、本人の同意なく医療機関や支援機関と情報をやり取りすることは原則として認められません。
これは単なる個人情報保護の問題ではなく、精神科医療・福祉支援における信頼関係の根幹に関わる問題です。
精神疾患を抱える方にとって、主治医や支援員は「安心して話せる唯一の存在」である場合も多く、企業との情報共有が勝手に行われたことを知った瞬間に、支援そのものを拒否してしまうことすらあります。
なぜ“本人の同意”がこれほど重要なのか?
- 精神医療では「本人の自律性・自己決定」が最も重要な原則であるため
- 精神疾患の有無や症状の程度は、極めてセンシティブな個人情報であるため
- 一度でも“勝手に情報をやりとりされた”と感じると、以降の支援関係に深刻な支障が出るため
したがって、企業側が「支援のために聞いているだけなんですが」と善意でアプローチしても、本人の同意がなければ、結果として本人の支援環境を壊してしまう可能性があるのです。
どんなときに専門機関との連携が必要になるのか?
連携が求められる具体的なケースは、以下のような場面です。
| シーン | 主な目的 | 関連機関 |
|---|---|---|
| 復職の可否判断を行うとき | 「いつから」「どの程度の業務内容で」復帰可能かを確認 | 主治医・産業医 |
| 支援の具体的な中身をすり合わせたいとき | 業務調整の方向性や職場での支援方法を検討 | 就労定着支援機関・ジョブコーチなど |
| 不調が続いており、客観的な状態を把握したいとき | 体調や治療の進捗を共有し、今後の方針を確認 | 主治医・精神科訪問看護ステーションなど |
| 面談時に本人の意見と企業側の認識が大きく異なるとき | 認識のずれを補正し、適切な合意形成を支援 | 支援機関の第三者的立場を活用 |
本人の同意取得のポイントと実務対応
連携を行うには、「何を、誰に、どのような形で提供・受領するのか」を明確にし、本人の書面または電子的同意を得る必要があります。
実務上の対応手順(例)
本人へのフィードバックも忘れずに
「主治医の先生からこういうお話がありました」と本人に丁寧に報告することで、透明性が確保され、信頼関係が維持されます。
本人に目的を丁寧に説明する
「復職の見通しを立てるために、主治医の意見を聞かせていただきたいのですが、ご協力いただけますか?」など、支援目的を明確にします。
情報提供依頼書(同意書)を提示する
提供先(機関名・担当者)、提供目的、提供内容、提供方法(電話・文書など)を明記したフォーマットを用意します。
本人から署名またはメールで同意を得る
メールでも法的には意思確認が可能ですが、記録が残るように文面管理を行います。
情報共有の同意取得の例(テンプレート)
件名:情報提供依頼のご相談
ご本人:◯◯様
このたび、就業支援の一環として、貴院(または支援機関)に対して以下の情報提供をお願いしたく、ご本人の同意を得ることが前提となります。
・提供先:○○クリニック ○○医師
・内容:現在の就業可否、業務上の配慮事項 などよろしければ、同意書へのご署名またはメールでの同意をお願いできますでしょうか。
このように、情報提供の目的、範囲、相手を明確に示すことがポイントです。
また、情報共有後は「何を共有したか」「本人にどのように説明したか」も記録に残すようにしましょう。
支援機関との連携:情報の一貫性と丁寧な伝達が信頼の土台に
精神疾患を抱える方の就労支援において、就労移行支援事業所、定着支援事業所、ジョブコーチ、精神保健福祉士などの支援機関は、企業にとって非常に心強いパートナーです。
これらの支援者は、医療機関と連携しながら、本人の生活状況や通院状況、就労希望などを継続的に把握し、職場定着に向けた支援を担ってくれる存在です。
しかし、こうした支援機関との連携は、単に「お願いすれば何とかしてくれる」ものではなく、企業側が積極的に“支援のチームメンバー”として機能する姿勢が必要です。
とくに、連携にあたっては次のような点に注意が必要です。
情報の「食い違い」が本人を混乱させる
支援機関が把握している本人の状況と、企業側が伝えている内容に食い違いがあると、本人は「どちらの話を信じていいのか分からない」と混乱したり、「自分のことが勝手に話されている」と不信感を抱いたりする可能性があります。
たとえば、
- 企業側が「そろそろ業務量を増やそうと考えています」と支援機関に伝えたが、本人にはその話が一切されていなかった
- 支援機関が「リモート勤務で安定してきた」と報告してきたが、実際にはチーム内で孤立感が高まっていた
こうした情報のズレを防ぐには、本人を中心に置き、共有内容を“当事者も理解・同意したうえで伝える”という基本姿勢を持つことが重要です。
支援機関との連携における基本マナーと工夫
連携時には、以下のような具体的な配慮を行うことで、支援の質を高めることができます。
1. 情報を一貫させる
- 支援機関に伝える情報は、本人に事前に伝えておく(「○○さんにお話しした内容を共有させていただきますね」)
- 「職場での現状」「今後の方針」「本人の希望」など、伝える項目は事前に整理し、簡潔かつ正確に伝える
- 支援機関とのやりとりを記録し、関係者間で共有(例:支援日誌、社内メモなど)
2. 面談内容の報告は、本人の了解を得てから
- 面談内容の共有は「支援のための連携であること」「本人の意向を反映するためであること」を明確にし、了承を得る
- 面談後に「○○さん、先ほどの内容を支援員さんにもお伝えしておいてよいですか?」と一言添えるだけでも信頼感が変わります
3. 環境や業務内容の変更があった際は迅速に共有
- 就業時間、業務の変更、異動、担当上司の変更など、本人にとって心理的影響の大きい変更事項は、支援機関にも即時共有
- 変更後の「経過観察」についても、企業・支援機関双方でモニタリング方針を共有しておくと効果的
支援者との「日常的な接点」が支援の質を高める
「問題が起きたときだけ連絡をとる」という関係では、信頼も連携力も生まれません。
むしろ、“問題が起きる前に相談できる”状態をつくることが、職場定着の成否を分けます。
支援機関との情報交換の習慣化に向けた工夫例
| 工夫 | 内容・メリット |
|---|---|
| 月1回の定例ミーティング | 支援機関と企業担当者で、本人の近況、配慮状況、今後の支援方針を共有する機会を設ける。オンライン実施でも可。 |
| Slackやチャットでの定期連絡 | フォーマルな連絡だけでなく、「最近の様子どうですか?」といった軽いやりとりが、早期発見・介入につながることも |
| 支援プラン共有シートの活用 | 業務内容・配慮内容・支援目標・確認担当者などを見える化し、支援の軸がブレないようにする |
- 主治医・支援機関との情報連携には、本人の同意が必須
- 同意書の文言・目的・提供先は明確に提示することが大切
- 主治医は「協働者」であり、ビジネス文脈を押しつけない配慮が必要
- 支援機関とは情報の一貫性と定期的な連絡体制を意識する
- 継続的に支援できる関係性を構築することが、企業・本人双方の安心につながる
面談に向けた業務
今後は、制度やツール、教育体制の整備によって、“属人的”な対応から“仕組みとしての支援”へと発展させていくことが求められます。
まとめ|面談の基本姿勢は「信頼と尊重」
精神疾患を抱える方との面談は、企業にとって「制度対応」や「リスク管理」の一環として捉えられがちです。
しかし、その本質はあくまで、“目の前の一人の社員と向き合い、共に働き方を整えていくための対話”です。
最終章では、ここまでの内容を振り返りながら、面談における最も重要なスタンス――「信頼」と「尊重」について整理していきます。
一方的に評価する場ではなく「対話の場」としての面談
精神疾患のある方との面談では、ともすれば「困っていることを指摘し、どうにか改善させる場」になりがちです。
しかし本来、面談は“対話”によって状況を理解し、支援や調整を共に考える場であるべきです。
「面談=対話」のための3つの視点
- 本人の語りを尊重する
➡ 沈黙を待つ、否定せず受け取る、話の主導権を奪わない - “できていること”に光を当てる
➡ 苦手な部分より、今できている工夫や安定している点に注目する - 支援を「押しつける」のではなく「選べる形」で提示する
➡ 「○○してはどうですか?」ではなく、「A案・B案で考えていますが、どう思われますか?」というスタンス
とりわけ、精神的な不調があるときには、「聞かれる」だけでも疲労感が強まることがあります。
だからこそ、“評価”ではなく“すり合わせ”の姿勢で臨むことが、安心と協力関係を生み出す第一歩になります。
専門家との連携と継続的な支援の姿勢が鍵
面談を一回限りのイベントで終わらせず、「継続的な支援のサイクル」にどうつなげていくかもまた重要なテーマです。
面談を「支援のスタート地点」と捉える
- 面談で明らかになった困りごとに対して、小さな支援を即時に始める
- 定期面談(例:月1回、四半期1回など)の仕組み化を検討する
- 本人の変化を観察し、必要に応じて支援機関や専門家にリレーする
支援を続けるには、人事単独では限界があります。
だからこそ、主治医や就労支援機関、産業医、場合によってはカウンセラーなどといった“多職種の連携”が、真の意味での支援を成立させる要です。
組織としての支援文化を育てる
- メンタルヘルス対応を属人化させず、マニュアルや研修を整備
- 「何かあったときにすぐ相談できる」心理的安全性を組織全体に醸成
- 精神疾患に対する偏見や無理解をなくすための啓発活動も視野に
こうした取組みが、「離職を防ぐ」以上に、“長く安心して働ける会社”としての信頼形成につながっていきます。
- 面談は評価の場ではなく、本人と共に働き方を調整する“対話の場”である
- 本人の語りを尊重し、安心して話せる関係性を築くことが最優先
- 面談を支援の出発点として、継続的なアクションを設計する
- 人事・上司・医療・福祉の多職種が連携し、支援の輪を広げていく
- 組織としての支援体制・文化を整えることが、真の安定雇用につながる
まとめ / チェックリスト
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 【1. 事前準備】 | |
| 面談の目的が明確になっているか | 採用判断・定着支援・復職支援など、目的を明確に設定したか |
| 配慮事項や既往歴を確認したか | 本人の同意のもと、過去の面談記録や配慮申出の有無を把握しているか |
| 面談内容を本人に事前に共有したか | 面談の目的・時間・話す項目を事前に伝え、不安を和らげたか |
| 面談記録フォーマットを用意したか | 誤解防止や記録残しのために記入様式を準備しているか |
| 【2. 面談実施】 | |
| プライバシーが確保された場所で面談したか | 周囲に聞かれない安心な場所・時間を確保できているか |
| 丁寧な導入と目的説明を行ったか | 「今日は〇〇について一緒に話しましょう」と安心感を伝えたか |
| 質問は具体的かつ負担が少ない内容にしたか | 一問一答形式や「はい・いいえ」で答えられる工夫をしたか |
| 不安や沈黙に対して落ち着いて対応できたか | 無理に急かさず、本人のペースを尊重したか |
| 本人の希望・状態・支援ニーズを整理できたか | どこに困りがあり、どんな配慮が必要か明確になったか |
| 【3. 面談後の対応】 | |
| 面談内容を記録し、必要な関係者と共有したか | 上司・産業医・支援員などと情報を一貫させたか(本人の同意前提) |
| 合意事項を本人にも共有したか | すれ違いを防ぐため、面談メモを本人と確認したか |
| 業務内容・就業環境の調整案を関係部署と協議したか | 配慮案(業務量・勤務時間など)を関係者と共有し調整したか |
| 次回面談やフォロー予定を設定したか | 一過性で終わらせず、継続支援の予定を立てたか |
ここまでで、精神疾患を抱える人材と向き合う面談の設計と実施、そして外部連携のあり方までを体系的に整理してきました。
実際の運用においては、「面談担当者のスキル・経験差」や「組織としての制度整備の未成熟さ」が課題として浮かび上がることも少なくありません。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
精神疾患を抱える方との面談は、難しさもありますが、決して特別なことではありません。
ほんの少しだけ、立ち止まって話を聴き、共に働き方を考える。その積み重ねが、職場に温かな風を運んでくれるはずです。
人事の皆さんのまなざしが、社員一人ひとりにとっての“安心の入口”となるように――そんな想いを込めて、本記事を締めくくらせていただきます。