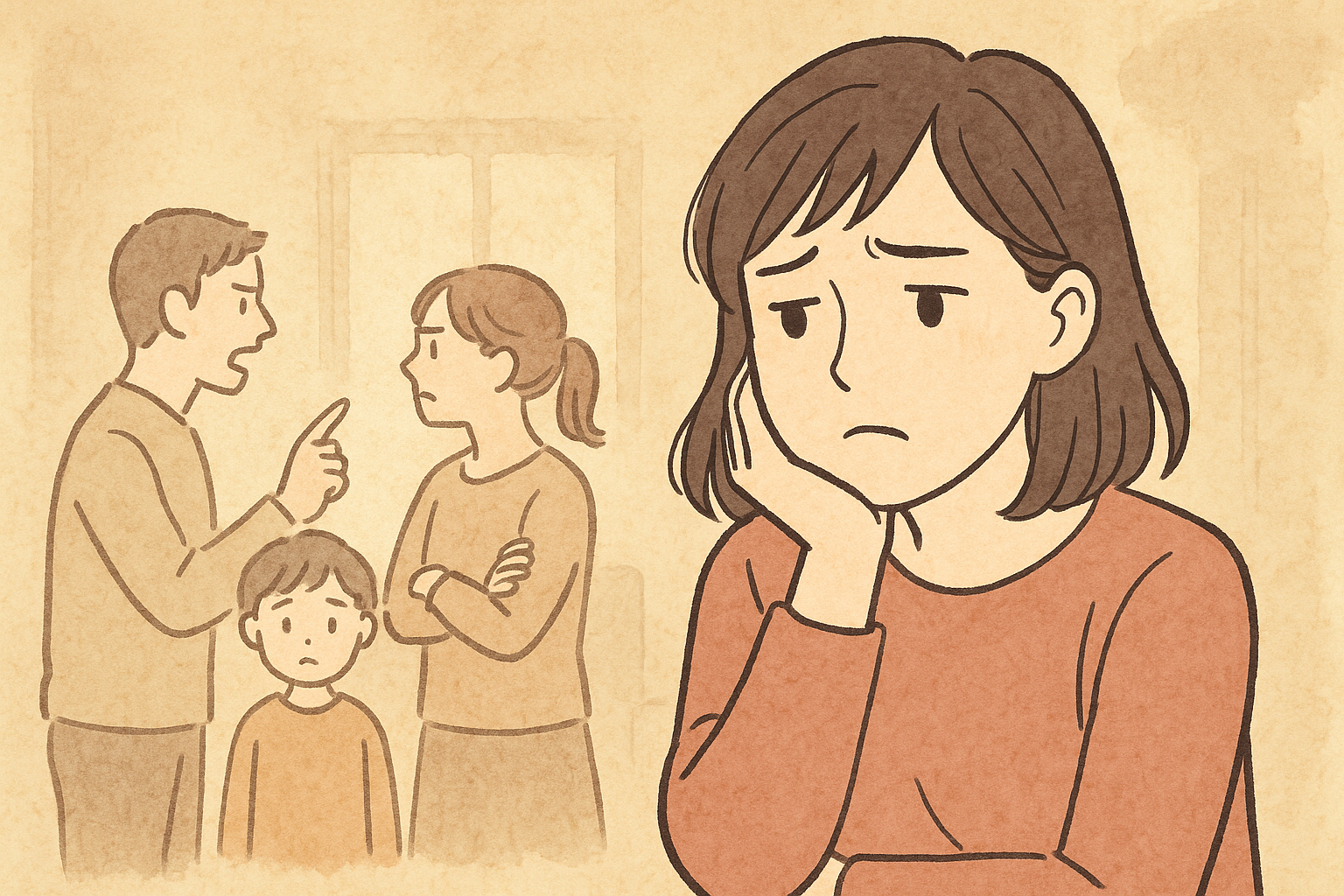家庭は本来、安心して心を休められる場所であるはずです。
けれど、誰かが支配的だったり、感情を抑え込まなければいけなかったりと、「家族の中でいつも緊張していた」という人も少なくありません。
そうした家庭は「機能不全家族」と呼ばれます。
外から見れば「普通の家族」に見えても、心の中では傷つきやすさや生きづらさを抱えていることがあります。
この記事では、機能不全家族の特徴や心理的影響、そして回復のステップを、心理学と精神医学の視点からわかりやすく解説します。
機能不全家族とは?――心理学的な定義と特徴
機能不全家族とは、家族という単位が本来果たすべき役割をうまく果たせなくなっている状態を指します。
この章では、機能不全家族の定義や特徴、そしてどのようなパターンがあるのかを丁寧に解説していきます。
機能不全家族の意味(心理学・精神医学における位置づけ)
「機能不全家族」とは、家族が本来持つべき基本的な機能――例えば安心感の提供、感情の共有、健全な育成環境の確保――が適切に果たされていない家庭を指します。
この言葉は心理学・精神医学の分野で用いられ、子どもの発達や大人になってからの人間関係・メンタルヘルスに深い影響を与える要因として注目されています。
精神疾患の診断基準として用いられているDSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル)において、機能不全家族という用語そのものは診断名ではありません。
しかし、多くの精神疾患や心理的課題――たとえば、パーソナリティの形成、情緒調整の困難、愛着障害(愛着スタイルの歪み)など――の背景要因として、機能不全家族の存在が言及されることがあります。
機能不全家族で育つと、子どもはしばしば「自分の感情よりも親の顔色をうかがう」ようになり、その結果、自尊心が育ちにくく、境界線(自他の区別)や人との距離感に問題を抱えるケースもあります。
「機能している家族」とはどういう状態か(支え合い・安全感・役割分担の視点から)
「機能している家族」とは、医学的・心理学的にはいくつかの要素に分けて考えることができます。
主なものは以下の通りです。
- 身体的安全と保護の提供
住まい、食事、衣服、健康管理など、基本的な生活環境を守る機能です。 - 情緒的な安全基地
家族が「安心して感情を出せる場」であること。恐怖や不安ではなく、受容や信頼が土台にあることが求められます。 - 役割の分担と柔軟性
親が親の役割を担い、子どもが子どもとして過ごせる環境。役割が逆転したり、固定化しすぎたりしていると、家族機能がゆがむリスクがあります。 - コミュニケーションの質
非難や無視ではなく、感情や考えを率直に、建設的に話し合えるかどうかが問われます。 - 価値観と規範の共有
家族ごとのルールや信念体系が、成員にとって納得できるものであるかも大切です。
極端な価値観の押し付けや、秘密の強制(家族内の「暗黙の掟」など)は、機能不全の兆候です。
これらの要素がバランスよく機能することで、子どもは「自分は大切にされている」という感覚=基本的信頼感を持つことができます。
逆に、これらのいずれかが欠けている家庭では、子どもは感情を抑えたり、過度に役割を背負ったりすることで「適応」しようとし、大人になってからその影響が現れることがあります。
- 機能不全家族とは、家族が本来の役割を果たせない状態を指す心理学用語
- DSM-5-TRやICD-11では診断名ではないが、リスク要因として重視される
- 家族機能は「安全」「感情」「役割」「規範」など多層的
機能不全家族にはさまざまなタイプがあり、それぞれに特有のパターンや苦しみがあります。
次の章では、「支配型」「放任型」「共依存型」など、具体的なタイプ別の特徴や事例を紹介しながら、あなたの家庭にどのような傾向があったかを一緒に考えていきましょう。
機能不全家族のタイプと具体例
機能不全家族とひとくちに言っても、そのかたちは家庭ごとに異なります。
「怒鳴られて育った」「親がまったく構ってくれなかった」「干渉されすぎて苦しかった」
――それぞれに異なる痛みがありますが、共通しているのは「家庭が安心できる場所ではなかった」という点です。
この章では、代表的な4つのタイプとその特徴をわかりやすくご紹介します。
支配型・コントロール型(権威主義・親の支配)
このタイプでは、親が強い権威を持ち、子どもに対して過度にルールや価値観を押し付ける傾向があります。
家庭内において「親が絶対」であり、子どもには意見や選択の自由がほとんど与えられません。次のような特徴がよく見られます。
- 「親の言うことに逆らうな」といった圧力がある
- 子どもの意見を聞かず、すべてを決めてしまう
- 「◯◯すべき」というべき論が支配的
- 体罰や威圧的な言動が正当化されている
支配型の親は、愛情表現のつもりで「正しく導いている」と考えている場合もありますが、子ども側には「自分らしく生きられない」「存在を否定されている」といった無力感や自己否定感が残りやすくなります。
このような家庭で育った子どもは、大人になっても人の評価に過敏だったり、「正しさ」にこだわりすぎて苦しくなる傾向があります。
支配型の家庭は、「境界線(バウンダリー)」が極端に曖昧で、親が子どもの人生を「所有物」のように扱ってしまうことが特徴です。
そのため、子どもが自分の人生を選び直すには、大きな心理的エネルギーが必要になることもあります。
放任型・無関心型(感情的な距離・ネグレクト)
このタイプの家庭では、親が子どもの感情や行動に関心を持たず、放任的であることが特徴です。
外から見ると「自由な家庭」と捉えられることもありますが、内側では子どもが深い孤独感を抱えていることが少なくありません。
よく見られる特徴としては:
- 子どもの話を聞かず、反応も乏しい
- 感情的な共鳴や共感が少ない
- 学校行事や生活面に無関心
- 基本的な生活管理(食事・衛生・健康管理など)すら放棄されている場合もある
心理学的には、このような家庭は「感情的ネグレクト(emotional neglect)」に分類されます。
たとえ暴力がなかったとしても、「誰にも理解されない」「大切にされていない」という感覚は、後のうつ病、不安障害、愛着障害などのリスクを高めることが知られています。
特にICD-11では、児童虐待の1つとして感情的ネグレクトが正式に記載されており、これは「存在の無視」が子どもの発達に与える深刻な影響を医学的にも認識している証拠です。
このような家庭で育った人は、大人になっても「人と深く関わるのが怖い」「人に頼れない」といった課題を抱えやすく、自分の気持ちをうまく表現できないまま孤立してしまうこともあります。
過干渉・共依存型(子どもを「生きがい」にする構造)
一見すると「仲の良い家族」に見えることも多いのが、過干渉型・共依存型の家庭です。
しかし実際には、親と子どもの心理的境界線があいまいで、子どもが「自分のために生きること」ができなくなってしまう構造が潜んでいます。
具体的には以下のような状況が含まれます:
- 子どもの進路・友人関係・恋愛まで過度に口を出す
- 親の感情を子どもがケアしている(逆転した役割)
- 親が「あなたがいないと生きていけない」と依存してくる
- 子どもが親を喜ばせることで存在意義を保っている
このような家庭では、親が子どもに過剰な愛情を注いでいるように見えても、実際は「親の寂しさや不安の穴埋め」として子どもを利用しているケースが多く見られます。
心理学ではこれを「共依存」と呼び、関係性の中でお互いの自我が損なわれる状態を指します。
共依存関係にあると、子どもは自分の感情やニーズを抑圧し続け、自立心を育てる機会を失ってしまいます。
このような家庭で育った子どもは、大人になっても「人の顔色をうかがいすぎる」「相手に尽くさないと愛されない」と感じ、人間関係で過剰適応に苦しむ傾向があります。
依存症・DV・精神疾患が背景にあるケース
最後に紹介するのは、家庭内にアルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症、DV(家庭内暴力)、あるいはうつ病・統合失調症・パーソナリティ障害などの精神疾患が存在しているタイプです。
こうした家庭では、日常が常に不安定で、次のような特徴が現れます:
- 親の情緒が日によって極端に違う(機嫌の浮き沈みが激しい)
- 家族内に「話してはいけないこと」がある(タブーの存在)
- 子どもが「家を守るために嘘をつく」
- 親の感情や行動が読めず、常に緊張している
たとえば、アルコール依存症のある家庭では、「外ではいい顔をしなさい」「パパのことは誰にも言っちゃだめ」といったメッセージが繰り返されることで、子どもが「家庭の問題を隠す役割」を担うようになります。
また、親に重い精神疾患がある場合、子どもが「親の介護役」や「励まし役」として振る舞わざるを得ないこともあります。
これは「ヤングケアラー(若年介護者)」と呼ばれ、社会的にも注目されている課題です。
このような家庭では、子どもは家庭内で安全を感じることができず、「生き延びること」が最優先になってしまいます。
その結果、大人になってからも「安心して人に頼る」「無防備でいる」ことが非常に困難になります。
- 機能不全家族には多様なタイプが存在する
- 支配型は、親の絶対的なコントロールが特徴
- 放任型は、感情的な無視や関心の欠如が本質
- 共依存型は、心理的境界線が曖昧になりやすい
- 依存症や精神疾患のある家庭では、日常が不安定で、子どもが役割を背負いやすい
機能不全家族で育つと、その影響は思春期や成人後にも色濃く残ることがあります。
次の章では、そうした家庭で育った人が抱えやすい「心の傾向」や「人間関係のパターン」について、心理学的な視点から詳しく解説していきます。
自分自身の生きづらさと向き合うためのヒントとして、ぜひ読み進めてみてください。
機能不全家族で育った人に起こりやすい心理的影響
機能不全家族の中で生き抜くために、子どもは自分なりの「適応戦略」を身につけていきます。
たとえば、感情を抑える、親の期待に過剰に応える、人に頼らないようにする――こうした行動は当時の自分を守るために必要だったものかもしれません。
ここでは、機能不全家族で育った人に多く見られる心理的影響を、心理学や精神医学の視点から具体的に解説していきます。
自己否定感・過剰な罪悪感
機能不全家族では、子どもが「家庭の問題の原因は自分にある」と思い込まされる場面が少なくありません。
たとえば、親が不機嫌になるたびに「自分のせいだ」と感じたり、愛されないことを「自分が悪いからだ」と受け止めてしまうのです。
このような経験が続くと、子どもの内面には以下のような感情が根づきやすくなります:
- 「どうせ自分なんて…」という自己否定的な思考
- 他人に迷惑をかけたくない気持ちが強く、自分の欲求を抑えてしまう
- 謝ることが習慣化し、「すみません」が口ぐせになる
- 失敗や拒絶に対して過剰に傷つき、回避的になる
これらは一見、謙虚さや思いやりのように見えるかもしれませんが、過剰になると自己価値感の低下や抑うつ傾向につながりやすくなります。
DSM-5-TRやICD-11では、自己否定や罪悪感はうつ病やパーソナリティ障害、発達性トラウマ障害の症状の一部としても位置づけられています。
つまり、単なる性格の問題ではなく、過去の体験に根ざした「心の反応」として捉えることが重要です。
人間関係でのパターン(支配・依存・過剰適応)
機能不全家族で育った人は、「人とどう関係を築けばいいのか」が分からないまま大人になります。
親との関係で身につけた対人パターンが、友人・恋人・職場の同僚との関係にも無意識に影響していくのです。
たとえば、次のような対人傾向が挙げられます:
- 相手をコントロールしたくなる(自分が支配されていたため、逆に支配しようとする)
- 依存的になりやすい(「見捨てられ不安」から相手にしがみつく)
- 相手の期待に過剰に応えようとし、自分を犠牲にする(過剰適応)
- 人と距離を詰めすぎる/逆に極端に避ける(愛着スタイルのゆがみ)
また、愛着障害の観点から見ると、「不安型愛着」や「回避型愛着」の傾向が強く出るケースもあります。
これは、親との間に十分な安心感を得られなかったことに起因し、他者との信頼関係に不安や混乱を抱きやすくなるのが特徴です。
職場・恋愛・家庭での再現
幼少期に身につけた心のクセや関係のパターンは、思春期以降の重要な人間関係においても繰り返されやすくなります。
これが「再演(再現)」と呼ばれる心理的現象で、特に以下のような場面で表面化しやすい傾向があります。
職場での再演
- 上司に対して過剰に従属的になる(支配的な親の影響)
- 評価されないと不安で常に過剰に働く
- 逆に、権威的な上司に強く反発してしまう
恋愛関係での再演
- 相手を「救おう」とする傾向(親の世話をしていた経験の再演)
- 相手に尽くしすぎる/または尽くされることに罪悪感を覚える
- 距離が縮まると不安になり、関係を壊してしまう
自分が親になったときの再演
- 自分の親と同じような言動をしてしまうことに気づいてショックを受ける
- 子どもに対して「こうあるべき」という価値観を押し付けてしまう
- 感情表現が苦手で、子どもとの距離感がうまくつかめない
こうした再演のパターンは、「気づく」ことから回復が始まります。
カウンセリングなどを通して、自分の行動パターンの背景を理解することで、より健全で自由な選択が可能になります。
アダルトチルドレンとの関連
「アダルトチルドレン(AC)」とは、機能不全家族で育ったことで、大人になってもなお心の中に深い影響を抱えている人々を指す言葉です。
正式な診断名ではありませんが、1980年代のアメリカで提唱されて以降、日本でも広く知られるようになりました。
アダルトチルドレンに見られる典型的な特徴には以下のようなものがあります:
- 他人の期待に応えようとしすぎて、自分の気持ちが分からなくなる
- 感情をうまく表現できず、抑え込みがちになる
- 「自分には価値がない」という根深い感覚
- 人に頼ることへの強い不安や罪悪感
- いつも孤独を感じているが、誰にも打ち明けられない
アダルトチルドレンの概念は、自己理解や回復のきっかけとして有効なツールとなりえます。
「自分はACだから一生治らない」と決めつけるのではなく、「今の生きづらさには理由があった」と気づくことが大切で、専門家のサポートを受けながら、自分自身との関係を少しずつ取り戻していくことは可能です。
特に、認知行動療法(CBT)やスキーマ療法、愛着修正を目的としたカウンセリングなどは、アダルトチルドレンに対して効果が示されています。
↓アダルトチルドレンについてはこちらで解説しています。
- 機能不全家族で育つと、自己否定感や罪悪感が根付きやすい
- 人間関係で支配・依存・過剰適応のパターンが出やすくなる
- 職場・恋愛・子育てにおいて過去の再演が無意識に起こる
- アダルトチルドレンという視点は、自分の苦しみに意味を与えるヒントになる
- 回復は可能であり、自己理解と支援の活用が鍵となる
次章への導入
では、こうした影響から少しずつでも回復していくには、どのようなステップがあるのでしょうか?
次の章では、「自己理解」「カウンセリング」「人との健全なつながりの回復」といった、実際の回復のプロセスと心理療法のアプローチについて解説していきます。
安心できる場所を取り戻すための第一歩として、ぜひ読み進めてみてください。
家族との関わり方を見直す――距離の取り方と境界線
機能不全家族で育った方が、心の回復を目指すうえで重要になるのが「家族との距離の取り方」です。
たとえ心に傷を負わせた相手が家族であっても、自分自身を守るためには適切な境界線を引くことが必要です。
この章では、「支える」姿勢への転換、感情的な巻き込まれを避ける方法、そして「許すか」「関わらないか」という選択を自分のためにどう位置づけるかについて考えていきましょう。
「助ける」ではなく「支える」姿勢を意識する
機能不全家族において育った方の多くは、「家族の問題を自分が何とかしなければならない」と感じてきた傾向があります。
たとえば、親の感情の起伏に過剰に反応してきた、兄弟の面倒を大人のように見ていた、など、子ども時代から“世話をする側”として育ってきたケースです。
これは「親を助ける子ども(Parentified Child)」と呼ばれる状態であり、心理学的には役割の逆転とみなされます。
しかし、回復の過程では「家族を助ける」ことから離れ、「必要であれば支える」程度の関わり方へと転換することが求められます。
支えるとは、相手が自分の責任で歩もうとするプロセスを見守ること。
無理に解決策を与えたり、問題に巻き込まれたりしない姿勢です。
たとえば、親が愚痴や不安を延々と話す電話に出るかどうか、距離を取る選択があってもいいのです。
相手が大人である以上、自分の感情や行動を自分で責任を持つべきであり、あなたが代わりに背負う必要はありません。
この切り分けは冷たく思われるかもしれませんが、自分を守るためには必要な境界線です。
これは「情緒的な自律」を確立する重要な一歩でもあります。
感情的な巻き込まれを避けるコミュニケーション
機能不全家族とのやり取りの中では、「自分が悪いのでは」と感じさせるような罪悪感の喚起や、怒りによるコントロールなど、非言語的・言語的な“巻き込み”が起きやすい傾向があります。
このような状況で自分を保つには、冷静で一貫したコミュニケーションスキルが必要です。
以下のような工夫が役立ちます。
- 応答に一拍置く(反射的に反応しない)
相手の言葉に即座に返答せず、「少し考えてから連絡するね」と距離を取るだけでも、感情の巻き込まれを回避できます。 - 「私」を主語にして話す(アイ・メッセージ)
「あなたはいつも…」ではなく、「私はこう感じている」と伝えることで、非難合戦になりにくくなります。 - 言い換えやスルースキルを使う
挑発的な言動に乗らず、「そう感じているんだね」と共感的に返すだけでも、巻き込まれを減らせます。
また、「連絡頻度」「会う頻度」「伝える情報の範囲」なども、自分で調整することが可能です。
連絡を義務ではなく“選択”に変えることができれば、関係性の主導権を自分に取り戻すことにもつながります。
これは単なるスキルではなく、「自分を守る」意識を具体的な行動に落とし込む手段です。
許す・関わらない、どちらも「自分を守る選択」
機能不全家族で育った人の多くが悩むのが、「許さなければいけないのか」「家族と縁を切ってもいいのか」という問いです。
結論から言えば、どちらを選んでも「間違い」ではありません。
大切なのは、それが「自分の心を守るための主体的な選択」であることです。
許すとは、必ずしも「関係を修復する」「すべてを水に流す」という意味ではありません。
むしろ、「もうこれ以上、自分の心を痛め続けることをやめる」という自己解放の意味合いがあります。
一方で、あまりにも関わることでダメージを受け続ける相手に対しては、距離を置く、あるいは関係を絶つという判断も、自分の安全と回復のために必要な選択肢となり得ます。
特に、暴力的・支配的・心理的に搾取的な関係が継続している場合、関係を維持することで回復が妨げられることがあります。
自分の感情を無視して「家族だから」と関わり続けることは、逆に“再トラウマ化”を引き起こす可能性があります。
回復のプロセスでは、「自分の人生の主役は自分」であるという感覚を取り戻していくことが大切です。
そのためには、家族との関係性も「義務」ではなく「選択」であると認識し直すことが求められます。
- 機能不全家族との関係では、「助ける」よりも「支える」姿勢が大切
- 感情的に巻き込まれないよう、冷静なコミュニケーションを意識する
- 許す・関わらない、どちらの選択も「自分を守る」行為として尊重されるべき
- 境界線を引くことは冷たいことではなく、自己尊重の表れ
悩んだ時の相談、カウンセリング先と支援
機能不全家族で育った方が、自分の心の回復を目指すうえで、専門家や同じ経験を持つ人たちとのつながりは大きな助けになります。
自力での回復には限界があるからこそ、適切な支援を受けることは「弱さ」ではなく「自己理解への勇気ある一歩」です。
この章では、相談できる専門職や支援サービスの種類について、わかりやすくご紹介します。
臨床心理士・公認心理師への相談
家族関係に関する悩みや、心の傷を丁寧に見つめ直したい場合、最も身近な相談先として「臨床心理士」や「公認心理師」が挙げられます。
これらはいずれも心理の専門職であり、大学院レベルの高度な教育と訓練を受けた国家資格保持者(公認心理師)または民間資格保持者(臨床心理士)です。
心理療法の選択肢
相談では、以下のような心理療法が用いられることが多くあります:
- 認知行動療法(CBT):ネガティブな思考パターンの修正に効果的
- スキーマ療法:幼少期からの深い思い込み(スキーマ)に焦点を当てる
- 内的家族システム療法(IFS):心の中にある“さまざまな自分”の声に耳を傾ける
機能不全家族で育った方は、自分の感じ方や考え方に対して「これでいいのかな?」と不安になりやすい傾向がありますが、心理士との対話を通じてその不安を少しずつほどいていくことができます。
費用と利用方法
カウンセリングは基本的に自費診療で、1回あたり5,000〜10,000円程度が目安です。
病院やクリニックの附属カウンセリング室、大学の相談室、地域の心理相談センターなど、様々な場所で受けることが可能です。
心理士は診断や薬の処方は行いませんが、丁寧な傾聴と心理教育を通じて、クライエントの「心の理解」を促すことに特化しています。
精神科・心療内科でのサポート
抑うつや不安、不眠などの症状が強い場合には、精神科や心療内科といった医療機関でのサポートが必要になることがあります。
特に以下のような症状が続いている場合は、早めの受診をおすすめします。
- 食欲や睡眠の著しい変化
- 動悸、過呼吸、パニック発作
- 死にたい・消えてしまいたいという思いが頭から離れない
- 集中力の低下、仕事や家事が手につかない
医学的な診断と治療
精神科医は、DSM-5-TRやICD-11などの国際的な診断基準に基づき、うつ病、不安障害、PTSD、愛着障害などの診断と治療を行います。
必要に応じて薬物療法(抗うつ薬、抗不安薬など)が併用されることもありますが、無理に薬を勧められることはなく、医師と相談しながら治療方針を決めていきます。
保険診療のメリット
精神科や心療内科の診察は保険が適用されるため、自己負担は原則3割です。
月1〜2回の受診で数千円程度と、心理士によるカウンセリングよりも経済的な負担が軽く済むことも多いです。
また、医療機関によっては心理士による保険診療内のカウンセリングを提供している場合もあります。
どこに相談すればいい?
お住まいの地域の精神保健福祉センター、市区町村の健康相談窓口などから、信頼できる精神科医を紹介してもらうことができます。インターネット上でも医師紹介サイトなどで調べることが可能です。
自助会・ピアグループ・オンラインカウンセリングなど
自分の経験を言葉にすることで、少しずつ心が整理されることがあります。
そのため、同じような背景を持つ人と出会える「自助会」や「ピアサポートグループ」は、大きな力になります。
自助会・ピアグループ
たとえば以下のような団体が全国で活動しています。
- アダルトチルドレン(AC)の自助会
- 毒親育ちの会
- トラウマ・DV被害者支援団体
こうした集まりでは、強制的に話すことは求められず、「ただそこにいて、話を聞くだけでもよい」というスタンスが一般的です。
同じ経験を持つ人の語りを聞くだけで、「自分だけじゃなかった」と感じられることもあります。
多くの会は無料または少額の参加費で運営されており、匿名での参加も可能です。
オンラインカウンセリング
近年は、スマートフォンやパソコンを使って自宅からカウンセリングを受けられる「オンラインカウンセリング」サービスも広がっています。
- 平日夜や土日でも利用できる
- 匿名でチャットやメッセージの相談ができる
- 地域に専門家がいない場合でも全国の心理士とつながれる
など、忙しい方や通院にハードルを感じる方にも適しています。
ただし、サービスの質には差があるため、心理士の資格の有無や相談実績、プライバシー保護の体制などを確認したうえで選ぶことが大切です。
- 回復には「専門家との対話」や「安全な場での共有」が効果的
- 臨床心理士・公認心理師は非医療的な支援で心を整理する助けに
- 精神科・心療内科では診断・薬物療法・医師との相談が可能
- 自助会やオンライン相談は「共感的なつながり」を築くために有効
- 相談の選択肢は複数あり、自分に合った支援を選ぶことが大切
最後に
機能不全家族で育った人が抱える苦しさは、決して「弱さ」ではありません。
むしろ、どんな環境でも生き抜こうとした「強さ」の証です。
家族の問題は一人では抱えきれないこともありますが、理解し、整理し、少しずつ距離を取りながら回復していくことが可能です。
心理的な癒しには時間がかかりますが、「知ること」「気づくこと」からすべてが始まります。あなたの生きづらさには、きっと理由があります。
ここから少しずつ、安心できる人間関係を築いていきましょう。
- 「機能不全家族」とは、家族の中で安心・信頼・尊重のバランスが崩れている状態
- 支配・放任・共依存など、形はさまざまだが「家族が機能していない」ことが共通点
- 心理的な影響として、自己否定感や過剰な罪悪感、共依存傾向などが生じやすい
- 回復には「自己理解」「境界線の見直し」「専門家との対話」が重要
- 自分を責めず、少しずつ“自分の感情”を取り戻していくことが大切
私たちは誰もが、家庭という小さな世界から自分の生き方を学びます。
けれど、そこで学んだ「生きるルール」が今のあなたを苦しめているなら、
それを手放すことも、立派な“成長”のひとつです。
どうか焦らず、少しずつ。
あなたの人生は、これから変わっていく力を持っています。
【参考文献】