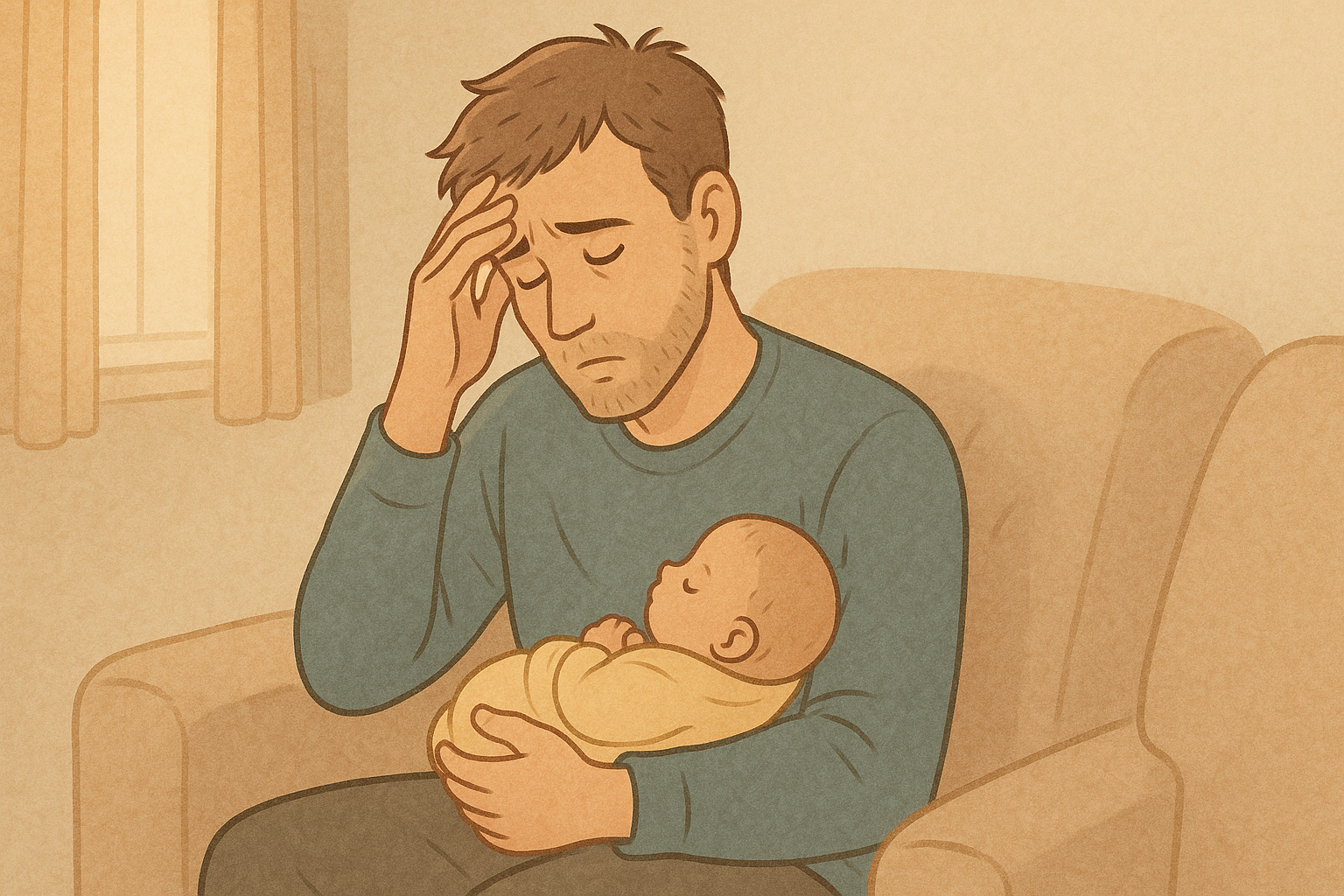赤ちゃんが生まれると、家族の生活は大きく変わります。
けれど、その変化の中で「なぜか気分が落ち込む」「イライラしやすくなった」「家にいるのがつらい」と感じる男性は少なくありません。
近年、「男性の産後うつ」や「父性うつ」という言葉が注目されています。
父親もまた、育児や仕事、家庭の変化によって心に負担を抱えることもあります。
この記事では、男性の産後うつの特徴や原因、セルフケア方法について、専門的な視点からわかりやすく解説します。
男性の産後うつ(父性うつ)とは何か
近年「父親も産後うつになる」という事実が注目されるようになってきました。
「育児うつ」「父性うつ」とも呼ばれるこの状態は、決して珍しいものではありません。
この章では、男性の産後うつの定義や背景、そして「男性がうつになるのはおかしい」といった誤解について丁寧に解説していきます。
用語と定義:「産後うつ」「父性うつ」「育児うつ」
「産後うつ」という言葉は、一般的には出産後の女性に起こるうつ状態を指します。
しかし、近年は男性もまた、パートナーの出産後にうつ症状を呈することがあると分かってきました。
これを指して、以下のような用語が使われます。
- 父性うつ(Paternal Postpartum Depression)
英語では“PPPD”と略され、医学的にも研究対象となっている症状です。パートナーの妊娠中または出産後に、父親がうつ状態に陥ることを指します。 - 男性の産後うつ(Male Postpartum Depression)
「母性うつ」に対する言葉として使われ、家庭内・育児・社会的プレッシャーなど複合的な要因によって引き起こされます。 - 育児うつ
男女を問わず、育児のストレスや生活の変化によってうつ状態になることを広く指します。医学用語ではありませんが、現場では広く使われています。
いずれも診断基準としては、DSM-5-TRやICD-11で規定される「うつ病性障害」や「適応障害」に該当することが多いとされています。
ただし、発症の時期や状況から「父性うつ」という表現が便宜的に使われています。
男性も出産後に鬱になる実態データ(発症率・時期)
「出産したのは妻なのに、なぜ夫がうつになるのか?」と不思議に思う方もいるかもしれませんが実際には多くの男性が育児期に心理的負担を抱えています。
複数の国際的研究によると、男性の約8〜10%が出産後3〜6か月以内にうつ症状を呈すると報告されています。
さらに、パートナー(妻)が産後うつを発症している場合、男性側も同時期にうつになるリスクは約2〜3倍に増加するといわれています。
日本の研究はまだ限られていますが、国内でも同様の傾向が報告され始めています。
特に育児に積極的に関わる父親、仕事のストレスが重なっている父親ほどリスクが高まるとされます。
男性が産後うつを発症しやすい時期
- パートナーの出産直後(0〜3か月)
- 育児休業明け、職場復帰時期
- 子どもの夜泣きや授乳対応などで睡眠が妨げられる時期
- 家庭内の役割分担がうまくいかない時期
このように、育児と仕事の「ダブル負担」によって慢性的なストレス状態となり、心身のバランスを崩す男性が増えています。
- 「父性うつ」は男性にも起こり得る、医学的にも認められたうつ状態です
- 男性の約8〜10%が出産後にうつ症状を経験する可能性があります
- 社会的な誤解や制度の壁が、男性のメンタル不調の気づきを遅らせています
男性が産後うつになる原因
父性うつを引き起こす原因は単一ではなく、仕事・家庭・社会的プレッシャーが複雑に絡み合っています。
とくに現代の男性は「理想の父親像」や「家計の担い手」としての役割を求められる一方で、家事や育児への参加も強く期待され、心身のバランスを崩しやすくなっています。
この章では、男性が産後うつになりやすい背景やリスク要因について、4つの側面から丁寧に解説していきます。
原因1:仕事・責任・役割のプレッシャー(家計・父親像)
男性が抱える最大のプレッシャーのひとつが、「家計を支え続けなければならない」という経済的・社会的責任です。
出産・育児によって支出が増え、妻が育休や退職で収入を減らす中、男性側のプレッシャーはさらに強くなります。
「理想の父親像」への圧力
現代では「優しい父親」「子どもと積極的に関わる父親」が理想とされます。
しかし、それを実現するには、働きながら育児にもフルコミットするという難易度の高い両立が求められます。
このギャップが「自分は父親として失格なのでは」といった自己否定感につながりやすくなります。
働き方とのジレンマ
- 長時間労働や残業
- 管理職としての責任
- 育休が取りにくい社風・制度
こうした要因が重なると、父親であることへの喜びを感じる余裕がなくなり、慢性的な疲労と焦燥感からうつ症状へと進展する可能性が高まります。
原因②:育児・家事・生活リズムの変化による睡眠不足と疲労
出産後の家庭は、生活リズムが激変します。
夜中の授乳・夜泣き・オムツ替えなどにより、睡眠の質や時間が著しく低下します。
睡眠不足はメンタル不調の主要因
睡眠が分断されると、前頭前野の働き(感情の制御や判断力)が低下し、怒りや不安をコントロールしにくくなります。
睡眠は単に「疲れを取る」ための時間ではなく心と体の両方を修復し、私たちが元気に日々を過ごすために欠かせない“脳のメンテナンスタイム”です。
睡眠には大きく分けて2つの種類があります。
- ノンレム睡眠(深い眠り)
- いわゆる「深い眠り」。
- 体がしっかり休まり、筋肉や免疫系が修復されると同時に、脳内で不要な情報が“掃除”されるとも言われています。
- レム睡眠(浅い眠り)
- レム睡眠は筋肉が弛緩し外的刺激で目覚めやすいことから「浅い眠り」と呼ばれる。
- 脳が活発に動き、感情の処理や記憶の統合が行われています。
- 特に、ストレスの記憶をやわらげる働きがあることが分かっています
これらは一晩のうちに約90分周期で交互に現れ、「睡眠サイクル」を形成します。
育児によってサイクルが崩れると、睡眠の質が低下し、感情コントロールや集中力、ストレスへの耐性が落ちてしまうのです。
原因③夫婦・パートナー関係の変化・孤立
出産を機に、夫婦関係の形が大きく変わります。
とくに産後の女性はホルモンバランスや育児負担で心身ともに不安定になりやすく、パートナー間の感情的距離が生まれることがあります。
コミュニケーションのすれ違い
- 「手伝ってるのに感謝されない」
- 「自分ばかりが育児している」
こうした相互の不満が蓄積されると、お互いに孤立感を抱きやすくなります。
そして男性は「弱音を吐けない」「相談しても分かってもらえない」と感じて黙り込みやすい傾向にあります。
原因④:社会・文化的な男性観・「我慢する男」の構図
日本社会では、今もなお「男は泣くな」「一家の大黒柱として我慢せよ」といった価値観が根強く残っています。
また男性向けの育児・メンタル支援制度はまだまだ不足しており、「誰に相談していいか分からない」状態が長引くことで症状が悪化しやすくなります。
男性が支援を求めにくい文化的背景
- 弱さを見せたら評価が下がるのでは
- 上司や同僚に「育児で疲れている」とは言いづらい
- 「うつかもしれない」と思っても病院に行きづらい
このような思い込みが、支援への第一歩を遠ざけ、孤立と悪化のスパイラルを招いているのです。
- 父親のうつは、仕事・家計・家庭内でのプレッシャーから生まれやすい
- 睡眠不足や生活の乱れもメンタル不調を助長する
- 夫婦関係のすれ違いや支援不足もリスク要因となる
- 男性特有の「我慢」「気づきにくさ」が、発見と支援の遅れにつながる
- 社会全体で、男性の育児・心の健康への理解と支援が求められている
次の章では、男性自身が「育児うつ」早期に気づき、対処するための「症状の特徴」や「セルフチェックの方法」について、具体的にご紹介していきます。
セルフ診断チェックリスト – 症状・サインを見逃さないために
育児や仕事に追われる日々の中で、「自分でも気づかないうちに心が疲れていた」ということは決して珍しいことではありません。
特に父親としての責任を感じている男性ほど、心の不調に蓋をしてしまいがちです。
この章では、男性にみられやすい産後うつの心理的・身体的なサインや、簡単に行えるセルフチェック項目をご紹介します。
典型的な心理的・行動的サイン(無気力・イライラ・集中力低下など)
男性の産後うつに見られる心理的な症状は、女性と似ている部分もありますが、表れ方には違いがあります。
以下のような状態が続いている場合、注意が必要です。
- 無気力感・意欲低下
趣味や楽しみにしていたことが面白く感じられない。仕事や家事に対するやる気が出ない。 - イライラ・怒りっぽさ
些細なことで怒りがこみ上げる。子どもの泣き声やパートナーの言動に過剰に反応してしまう。 - 集中力の低下・思考の鈍化
仕事中にミスが増えた。書類やメールの内容が頭に入らない。読書やテレビすら集中できない。 - 罪悪感・自己否定
「父親失格かもしれない」「何もできていない」と感じる。自分に価値がないように思えてくる。 - 感情の起伏が激しくなる
突然涙が出る、逆に無感情になるなど、情緒が不安定になることがあります。
こうした症状は、ICD-11でもうつ病の基準の一部として明記されており、2週間以上続く場合は「抑うつエピソード」と判断される可能性があります。
また、男性の場合、「仕事に逃げる」「アルコールやゲームで現実逃避する」といった“行動で隠す”傾向もあります。
うつ症状が「過活動」や「怒り」として表れるケースも多いため、内面的な苦しさに気づきにくいのが特徴です。
身体的・睡眠・食欲の変化(不眠・食欲低下・過食など)
心の疲れは、体の不調として現れることもあります。
以下のような変化が見られた場合、身体からの「危険サイン」かもしれません。
- 睡眠の質の低下
夜中に何度も目が覚める/寝つきが悪い/早朝に目が覚めてしまう/寝ても疲れが取れない - 食欲の変化
まったく食欲が湧かない、もしくは過食が止まらない。特に炭水化物や甘いものに偏る場合も。 - 頭痛・肩こり・胃腸の不調
慢性的な体の痛み、腹痛、下痢や便秘などが続く場合、ストレス由来の身体症状である可能性があります。 - 疲労感・倦怠感
十分に休んでも疲れが抜けない。体が重く感じる。 - 性欲の低下
ホルモン変動や心理的要因により、性的関心が著しく下がることもあります。
これらの身体症状は「男性ホルモン(テストステロン)低下」や「慢性ストレス」に起因しており、精神疾患の一部として現れることもあります。
精神診断マニュアルであるDSM-5-TRやICD-11では、こうした身体的変化も診断評価の一要素として重視されています。
セルフチェックリスト:まず自分で確認できる項目
以下は、父性うつの早期発見に役立つ簡単なセルフチェックリストです。
該当する項目に多くチェックがついた場合は、専門機関への相談を検討してください。
- □ 以前よりイライラしやすくなった/怒りっぽくなった
- □ 最近、気分が沈みがちで何をしても楽しくない
- □ 集中力が低下し、仕事や家事に支障が出ている
- □ よく眠れない、または眠りすぎてしまう
- □ 食欲が落ちた、または過食気味になっている
- □ 疲れやすく、朝から体がだるい
- □ 自分はダメな父親だと感じてしまう
- □ 子どもと関わるのが苦痛に感じることがある
- □ パートナーとの会話が減った/すれ違いが多い
- □ 以前は楽しめたことに興味を持てない
- □ 酒やネットに依存気味になっている気がする
これらのうち5つ以上に該当し、それが2週間以上継続している場合は、うつ病エピソードの可能性が考えられます。
なお、たとえ3〜4項目であっても、本人が「つらい」と感じているなら早めの相談が重要です。
伴いやすい家庭・仕事への影響(夫婦関係・育児・職場)
産後うつの影響は、本人だけでなく周囲の人たちにも広がっていきます。
特に以下のような影響が見られる場合、放置せず対応することが望まれます。
家庭への影響
- パートナーとの衝突やすれ違いが増える
- 会話やスキンシップが減り、夫婦関係が冷え込む
- 子どもとの関わりが減少し、育児の喜びを感じにくくなる
- 「家にいるのが苦痛」と感じてしまう
育児への影響
- オムツ替えや夜泣き対応などに非協力的になる
- 子どもに対して「かわいい」と思えなくなる
- 過干渉、または無関心という両極端な関わり方になる
職場への影響
- 遅刻・欠勤・ミスが増える
- 人間関係がうまくいかなくなる
- 仕事のパフォーマンスが著しく低下する
- 「辞めたい」という気持ちが強くなる
このように、父性うつは“静かなSOS”として日常の中に現れます。
早期に気づき、正しい対応を取ることで、悪化を防ぐことが可能です。
- 男性の産後うつは「怒りっぽさ」「無気力」「集中力低下」など心理面に加え、身体症状でも表れやすい
- 自覚しにくいため、セルフチェックで振り返ることが重要
- 「仕事でカバー」「我慢」で乗り越えようとせず、早期の相談・支援が回復の鍵
- 家庭や仕事にも波及するため、“本人だけの問題”ではない
- 2週間以上続く症状や日常生活への支障がある場合は医療機関へ
セルフチェックの結果、自分にもいくつかの項目が当てはまるかもしれない
――そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。では、そんなとき、どのように行動すればいいのでしょうか?
次の章から「父性うつ」の予防策や、すでに不調を感じている場合に実践できるケア方法、相談先や治療の流れについて、詳しく解説していきます。
あなたやご家族の心が少しでも軽くなるヒントを見つけていただけたら幸いです。
専門のメンタルケア支援や休職制度について
「もしかしたら、自分は父性うつかもしれない」
——そう気づいても、いざ行動に移すのは勇気がいることかもしれません。
でも、心の不調は“我慢すれば治るもの”ではありません。
適切な支援を早期に受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を守ることができます。
この章では、男性の産後うつに対して利用できる専門支援、自治体の制度、職場での支援など、相談先と活用方法を幅広くご紹介します。
メンタルヘルス専門機関(心療内科・精神科・カウンセリング)
父性うつは医学的に「抑うつ障害(depressive disorder)」の一形態とみなされ、ICD-11にも記載されている正式な疾患です。
そのため、医療機関での専門的な評価とサポートが有効です。
心療内科・精神科
うつ病の診断と治療を行う専門医療機関です。
医師による問診・評価を通じて、以下のような治療が検討されます。
- 対話療法(認知行動療法など)
思考の偏りや感情のパターンを整理し、現実的な対処法を身につけるサポートが行われます。 - 継続的なモニタリング
症状の変化を追いながら、無理のないペースで回復を目指します。 - 薬物療法(抗うつ薬・睡眠薬など)
状態に応じて適切な薬剤を処方。副作用や飲み合わせなどについても丁寧に説明されます。
男性の場合、「自分はうつではない」と思い込み、受診をためらう方も少なくありません。
しかし、専門家の視点を借りることで、客観的に自分の状態を整理することができます。
臨床心理士・公認心理師とのカウンセリング
薬を使わず、対話によるサポートを希望する場合は、心理カウンセリングも選択肢になります。
- 夫婦関係や育児のストレスを整理したい
- 誰かに話を聴いてもらうだけでも楽になる気がする
- 「怒りっぽさ」「イライラ」といった症状の背景を探りたい
といった場合に、有効です。
地域のメンタルクリニックやカウンセリングルームなどで、保険適用・自費いずれの形でも利用可能です。
育児休業制度の活用
男性の育休取得率は年々上昇していますが、いまだに「取りにくい」と感じている方も多いのが現実です。
しかし、うつの予防や夫婦関係の安定のためにも、育休は重要な制度です。
- 育休中の給与補償(育児休業給付金)
給与の約67%(一定期間後は50%)が支給されます。 - 育児目的休暇制度(自治体・企業独自)
育休以外でも、子どもの通院やイベント参加のために休める制度もあります。
育児と仕事を無理なく両立させるためにも、これらの制度の存在を知り、必要に応じて使う意識が大切です。
職場・産業保健・休職・復職支援の視点
職場での理解とサポートもまた、父性うつからの回復を左右する大きな要素です。
「仕事に支障をきたしているかもしれない」と感じたら、職場内の支援制度や産業保健スタッフを活用することを検討してみましょう。
産業医・保健師への相談
職場に産業医や産業保健スタッフがいる場合は、以下のような支援が受けられます。
- 精神的な不調の相談・アドバイス
- 簡易なメンタルヘルスチェック
- 医療機関の紹介
- 就業上の配慮(勤務時間の調整など)についての提案
「人事には言いづらいけど、誰かに相談したい」と思ったときには、信頼できる窓口となります。
休職・復職支援制度の活用
長引く不調が続く場合には、「いったん休む」という選択も有効です。
- 傷病手当金の申請(健康保険加入者)
医師の診断書があれば、給与の約2/3が支給されます。傷病手当は最長1年半支給されます。 - 職場の復職支援プログラム(リワーク支援)
段階的な復職に向けての準備が可能です。 - 上司・人事との連携
症状を抱えながらも働き続けられる方法を一緒に探していく対話が重要です。
企業によっては、EAP(従業員支援プログラム)として外部カウンセリングを無償で提供しているケースもあります。
「制度があるのに知らなかった」とならないよう、就業規則などを確認しておくと安心です。
- 父性うつは専門的な評価・治療が有効な“疾患”であり、医療機関の受診が回復への近道
- 心療内科・精神科・心理カウンセリングなど、多様な支援手段が存在する
- 職場には産業医・保健師・EAPなどのサポート体制があることも
- 必要であれば、育休・休職・復職支援制度を使って“立て直す時間”を確保してよい
自宅でできるセルフケア、改善策
この章では、父性うつのリスクがある方、あるいはすでに不調を感じている方が実践できるセルフケアや、家族との連携、生活習慣の見直しについて、段階的にご紹介します。
まずできること:休息・睡眠・育児分担・夫婦コミュニケーション
まず最初に意識したいのは、「今の自分に必要なのは“休むこと”かもしれない」という視点です。
心身が疲れきっているときには、複雑な対策よりも、基本的なニーズを満たすことが最優先となります。
休息と睡眠を確保する
産後の生活では、父親であっても夜間の授乳サポートやおむつ替えなどで睡眠が断続的になりがちです。
特に睡眠不足は、感情のコントロール機能を担う前頭前野の働きを低下させ、イライラや抑うつを悪化させる一因になります。
- 短時間でも質の高い仮眠を取る
- パートナーと交代で夜の育児を分担
- 就寝前にスマートフォンを触らず、照明を落として入眠を促す
など、小さな工夫が心の安定に大きく貢献します。
育児と家事の分担を見直す
「父親だから、全部を支えなければ」というプレッシャーを抱えすぎてしまう方もいます。
しかし、育児は本来“家族の協働作業”です。役割を固定せず、「今日は誰が何をやるか?」を日々柔軟に話し合うことが、精神的な負担を和らげてくれます。
家族・パートナーとの協力:「話す・共有する・支える」
父性うつの回復において、家族との関係性は大きなカギを握ります。
一人で抱え込まず、「話す」「共有する」「支え合う」関係を築くことが、早期回復に向けた土台となります。
気持ちを“隠さず話す”ことの大切さ
「男なんだから強くあれ」「弱音を吐くなんて情けない」といった価値観は、父性うつの気づきと回復を遅らせる要因です。
「最近ちょっときつくてさ」「イライラしやすいんだよね」と、あえて小さく打ち明けてみることが、孤独の殻を破るきっかけになります。
パートナーと“感情”を共有する
不調を抱えると、パートナーとの関係にもすれ違いが起こりやすくなります。
「言わなくてもわかってくれるだろう」ではなく、「わかってもらうために言葉にする」姿勢が大切です。
- 「何がしんどいのか」を具体的に伝える
- 「どうしてほしいのか」を感情に沿って共有する
- 「一緒にどう乗り越えるか」を相談する
これにより、夫婦の信頼関係が深まり、不調の悪循環を断ち切る力になります。
生活習慣の見直し:運動・食事・趣味・リラックス時間
心の健康は、生活リズムと密接に関係しています。
些細に思える習慣でも、整えることでメンタルヘルスは大きく改善されていきます。
運動の習慣
軽い運動は、脳内でセロトニンやエンドルフィンといった「幸せホルモン」の分泌を促し、気分の安定に効果があります。
ジムに行かなくても、以下のような小さな習慣から始められます。
- 10〜15分の散歩
- 赤ちゃんをベビーカーで連れていく外出
- 子どもと一緒に体を動かす遊び(抱っこスクワットなど)
運動は、ストレスホルモン(コルチゾール)の低下にも寄与するため、継続することで予防効果も期待できます。
栄養バランスを意識した食事
忙しい中でも、以下のような点を心がけるだけでも効果があります。
- 朝食を抜かない
- 加工食品や糖質中心の食事を控え、タンパク質やビタミン・ミネラルを取り入れる
- 発酵食品(納豆・ヨーグルト)など腸内環境を整えるものを意識的に摂る
腸と脳は「腸脳相関」としてつながっていることが科学的にも示されており、腸の状態がメンタルに影響することがわかっています。
趣味・リラックスの時間を取り戻す
赤ちゃん中心の生活になると、自分の趣味や「一人の時間」は後回しになりがちですが、完全に失ってしまうとメンタルのバランスが崩れやすくなります。
- 1日5分でも「好きな音楽を聴く」「ゆっくりお茶を飲む」
- パートナーに協力してもらい、週に1〜2回でも趣味の時間を確保する
- SNSやネットから一時的に離れて「情報疲れ」を減らす
自分を大切にする時間は、結果的に子どもやパートナーにも優しく接する余裕につながります。
- 睡眠や休息をしっかり確保することが心身回復の第一歩
- 夫婦での感情共有・育児分担が“孤独な父性”を和らげる
- 軽い運動や食事改善も、メンタルヘルスに大きな効果がある
- 趣味・リラックス時間を持つことは“自分を守る手段”
- 家族・地域の支援を「遠慮なく使う」姿勢が予防・回復につながる
最後に
男性の産後うつ(父性うつ)は、決して珍しいことではありません。
責任感の強い人ほど、「自分がしっかりしなければ」と抱え込み、気づかぬうちに心が疲れてしまうことがあります。
けれど、早めに気づき、休息や相談を取り入れることで、回復の道は必ず開けます。
あなたが感じている不調は「弱さ」ではなく、「助けを求めるサイン」です。
- 男性もホルモンや生活変化の影響で「産後うつ」になることがある
- 主なサインは、気分の落ち込み・イライラ・無気力・不眠・食欲の変化など
- 原因には、仕事と育児の両立、睡眠不足、孤立感、夫婦関係の変化が関係する
- 休息・夫婦での共有・専門機関への相談が回復の第一歩
- 精神科・心療内科・自治体の相談窓口など、支援の選択肢は複数ある
「父親が笑顔でいられること」は、家族全体の幸せにもつながります。
無理をせず、あなた自身の心を守ることを大切にしてください。
もし「少ししんどいな」と感じたら、一人で抱え込まず、専門家や身近な人に話してみましょう。
その一歩が、あなたと家族を守る大切なスタートです。
【関連記事】
【参考文献】
・Prevalence of paternal depression in pregnancy and the postpartum: An updated meta-analysis